戦後教育史学習会ニュース№16
| 市民学習会 第15回戦後教育史を学ぶ 針谷順子先生のライフヒストリーを聞く 幾世橋小は教育の原点(抄) 〒371-0026群馬県前橋市大手町3-1-10 教育会館内 ℡&fax027-235-8876 ‘04.9.21(月) 群馬県高校教育研究所発行:編集/橋本寛文 |
 ‘04年9月11日(土)、前橋市総合福祉会館で標記の学習会が開催されました。「幾世橋小学校」は子どもたち全員が分かるまで教えてくれる“戦後民主主義”を地でいく学校でした。それを教育の原点と考える針谷先生は高校生と正面から向き合うことによって教師としての自己形成と取組みました。その誠実な足跡が卒業生に刻まれていきました。先生のお話に触発され、参加者の意見・感想が飛び交い、充実した学習会となりました。なお、正確を期すため一部加筆・訂正、追録があることをお断りしておきます。
‘04年9月11日(土)、前橋市総合福祉会館で標記の学習会が開催されました。「幾世橋小学校」は子どもたち全員が分かるまで教えてくれる“戦後民主主義”を地でいく学校でした。それを教育の原点と考える針谷先生は高校生と正面から向き合うことによって教師としての自己形成と取組みました。その誠実な足跡が卒業生に刻まれていきました。先生のお話に触発され、参加者の意見・感想が飛び交い、充実した学習会となりました。なお、正確を期すため一部加筆・訂正、追録があることをお断りしておきます。*******************
司会:針谷順子先生のご紹介をさせていただきます。先生は1945年神奈川県横須賀にお生まれになりました。その後、福島県双葉郡幾世橋村に移られ(太平洋岸、いわき市の北)、1951(昭26)年幾世橋小学校に入学しています。この 幾世橋小学校こそが針谷先生にとっての唯一の“母校”、しかも、教育の原点だと思うので、皆さんに是非ご紹介していただこうということで、今日お出でいただきました。福島出身なのに群馬県で教職生活の理由ですが、お連れ合いが群馬県出身である関係でして、1967年、市*******************
立太田商業高校で教員生活をスタートさせ、藤女、中央高校を歴任、現在高商で国語を担当なさっております。来春、ご退職の予
定だと伺っています。よろしくお願いします。
1.作文を喜ぶ家庭は民主的家庭です
平野:先生の出身校は、と聞かれたら迷わず「幾世橋小です」とお答えになるとおっしゃっていますが、「幾世橋の子」という文集の創刊の辞を校長先生が書いておられますね。この中にどんな趣旨でこの文集を発行したのかが書かれていますので、まず、読んでみたいと思います。
父兄の皆様へ 笠原一美
戦後の新教育では作文の時間が特に設けられていないから、作文なんか、あまりやらなくてもいいのではないか、というように考えている方があるとしたら、それは大へんなまちがいだと思います。むしろ作文の時間が特設されていないので、作文をやる機会はずっとふえてきているのです。
あらゆる学習の記録や発表には必ず作文的な仕事が必要なのです。そして、作文は單なる技術ではなくて、ものの見方、考え方を深く、正しく育てていく教科、人間教育のための教科です。
子供が喜んで作文を書く家庭、そして父も母もそれをよく理解している家庭は、きっと民主的な家庭だと思います。
図画で子供が上手に父を冩生されたら確かに喜ばれるでしょう。と同様に子供が上手に、ありのまま、父を冩生されたら喜んでいただきたいのです。
作文指導の教室も亦、民主的な教室です。それは言論の自由がたっとばれているからです。生活の眞実が何より大切にされているからです。
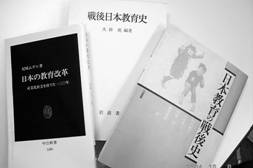 この点を深く考えていられる先生方は作文教育を重視されて兒童の指導に努力されています。尚一歩前進を考えていられる先生方は衆議一決、ここに兒童文集「幾世橋の子」第一集を発行するに致しました。発行については、先生方に非常な手数とお骨折をかけますので、私は考えましたが、先生方はよい子のために、進んでやろうとの気構え、私にとってこんなに嬉しいことはありません。こうした熱心な先生方と共につとめ得ます身の幸福を、私はつくづくありがたく感謝しています。ご家庭の皆様にも大いに喜んでいただきたいと思います。この無邪気な子供達は何を考え、世の中を如何に見、そして何をのぞんでいるでしょうか。兒童の生活はどうでしょうか。文はつたなくても考えさせられる点は多々あります。子供たちのために吾々大人は何をなすべきか。
この点を深く考えていられる先生方は作文教育を重視されて兒童の指導に努力されています。尚一歩前進を考えていられる先生方は衆議一決、ここに兒童文集「幾世橋の子」第一集を発行するに致しました。発行については、先生方に非常な手数とお骨折をかけますので、私は考えましたが、先生方はよい子のために、進んでやろうとの気構え、私にとってこんなに嬉しいことはありません。こうした熱心な先生方と共につとめ得ます身の幸福を、私はつくづくありがたく感謝しています。ご家庭の皆様にも大いに喜んでいただきたいと思います。この無邪気な子供達は何を考え、世の中を如何に見、そして何をのぞんでいるでしょうか。兒童の生活はどうでしょうか。文はつたなくても考えさせられる点は多々あります。子供たちのために吾々大人は何をなすべきか。
私どもは、これを手がかりとして、又、新しい指導に精進致す覚悟でおります。そして又第二集をと考えて居ります。御協力を期待してやみません。
50年代に入りまして、『やまびこ学校』が出て、生活綴方復活の機運が高まっている中で、もう高らかな生活綴り方宣言といっていいような創刊の辞だと思います。この「幾世橋の子」という文集について、当時生徒として体験された針谷先生に伺っていきたいと思います。
針谷:私がなぜこの場に出てきたかと言いますと、自分はもう来年3月に退職するわけですが、(教師としてだけではなく)自分の原点になっているものを考えてみますと、やはり幾世橋小学校の教育だったんだという思いが強くなり、是非皆さんにも知っていただきたいと思ったからです。この幾世橋小学校がどこにあるかといいますと、福島県の太平洋岸でいわき市の少し北にあたる半農半漁の小さな村の小学校です。群馬には斉藤喜博さんの島小学校という大変有名な実践校がありましたが、幾世橋小はどこにも知られないような小さな小学校です。でも、そういう小さい小学校で、子どもた ちのために力を注いでくれた先生方がいらっしゃたということを、語り伝えていくのはもう私くらいしかいなくなったという気がします。幾世橋小学校の教育の中で、特に印象に残っているのがこの兒童文集「幾世橋の子」なのです。創刊号が出されたのが1952(昭27)年、私が2年生の10月でした。基本方針は全校児童の作品‐文章・詩・俳句、観察記録も入りますか、全校児童の書いたものを、載せるということなんです。では、全校で何人くらいいたかというと、私のクラスは58人で、もう二人増えると2クラスになるんだけど、先生方がさもあと二人いるように教室の片隅に机を2つ置いて、二学級にしたんです。全校で大体320名くらいだったでしょうか。そういう小さな村の学校でした。でも、全部の子どもの作品を載せることは1回では済まないわけで、昭和27年度に3冊出しているんです。当時はみんな手作りのガリ版印刷ですよね。驚くのはこの表紙です。カラーの4色刷りなんです。どうやってこれを印刷したのかと思うんですけど、表紙絵も素晴らしいですよね。女の先生が描いて印刷してくださったんですが、どんな気持ちで印刷してくださったのかなと、(教員という立場になって)今考えてみても感心するばかりですね。この文集の中で、印象に残っているのは、特に第2集の巻頭詩なんですね。黒地に白いインクの印刷なんて凝っていますよね。4年生の池田君の「ちょうなん」という詩です。
ちのために力を注いでくれた先生方がいらっしゃたということを、語り伝えていくのはもう私くらいしかいなくなったという気がします。幾世橋小学校の教育の中で、特に印象に残っているのがこの兒童文集「幾世橋の子」なのです。創刊号が出されたのが1952(昭27)年、私が2年生の10月でした。基本方針は全校児童の作品‐文章・詩・俳句、観察記録も入りますか、全校児童の書いたものを、載せるということなんです。では、全校で何人くらいいたかというと、私のクラスは58人で、もう二人増えると2クラスになるんだけど、先生方がさもあと二人いるように教室の片隅に机を2つ置いて、二学級にしたんです。全校で大体320名くらいだったでしょうか。そういう小さな村の学校でした。でも、全部の子どもの作品を載せることは1回では済まないわけで、昭和27年度に3冊出しているんです。当時はみんな手作りのガリ版印刷ですよね。驚くのはこの表紙です。カラーの4色刷りなんです。どうやってこれを印刷したのかと思うんですけど、表紙絵も素晴らしいですよね。女の先生が描いて印刷してくださったんですが、どんな気持ちで印刷してくださったのかなと、(教員という立場になって)今考えてみても感心するばかりですね。この文集の中で、印象に残っているのは、特に第2集の巻頭詩なんですね。黒地に白いインクの印刷なんて凝っていますよね。4年生の池田君の「ちょうなん」という詩です。
最後に先生が短い批評を書いてくださっているんですね。私は教師になってからも何度も何度も読み返していますが、笠原校長先生の創刊号の辞、その編集後記(註)の教頭の長浜先生の言葉に、新時代の息吹きを感じてきました。
編集後記で長浜教頭先生は次のように書いています。生徒の作文を読んで気になるのは何か現実をみんな割り切った形で書いているという点、お母さんは働いている有難う、感謝する、自分も大きくなったら恩を返したいみたいな何か現実をそのまま割り切って受け止めているという点が非常に気になる、なぜお母さんは朝から晩まで働きゃなんないのか、大変な思いをしなければならないのか、そのなぜというところに眼を向けて鋭く考えていくというその点が弱い、そこに心もとなさを感じる、という評です。ですから、笠原先生も長浜先生も学校の管理者が学校の教育実践のリーダーとなっていた、リーダーになることができた人たちなのだ、そういう学校の中で一人ひとりの生徒がものを書くように、考えるように、そして、一人々が書いたもの、どれが優れているとかそういうのでなくて、それを大事にして育てていこうとするような教育がされたのではないのかということを感じています。これを回しますので、見てください。
それで、「幾世橋の子」は、3号しか残っていないんです。どうしてなのかな、と思っていたら、その翌年、校長先生が退職、長浜先生が転勤し、新しい教頭先生を中心にして、「幾世橋の子」が出されているのですが、活版刷りなんですね。とっても綺麗になっているのですが、その活版刷りの文集は周囲からも評価されるのですが、それで終わりなんです。どうしてでしょうか。平野先生は歴史的な流れがあるとおっしゃっていますが、それだけではないような気もします。その点については皆さんにも考えていただきたいと思います。
(註)編集後記(抜粋)
○自然観照の文というか、また、生活観照の文というか…自然や日常の生活をそのままに、しかも割り切れた姿で書きあらわしている傾向が多く見られるのは、新教育の成果としては考えざるを得ない。世の中の多くが、このまま固定してよい筈は決してないと思う。誰でも現実には日常それを考えどおしであり、行いどおしである。それを文化といい、創造の生活というので、同じ自然を題材にとっても、そこに繰りひろげられた自然に郷土人の発展の道、仕合せの道を発見し、考えていくための疑問や抱負を子供なりに持っているわけであろうし、社会科でも何科でもその点は強調されているのにと思う。子供らは作文と教科とを何か別々なものと考えているのではなかろうかと思われて、悲しくさえなる。母に題をとり、母の多忙がどこから来るのか、どうしたらそれが合理化されるかを考える心まで上級生には欲しいと思うのである。感謝だけや早く大きくなったら母に楽をさせたいだけの気持ちでは、現実の母の多忙は少しも減じないのである。それに対する検討と努力から文化が創造され、発展するのではなかろうか。全て割り切っているふうに感ぜられるこどもらの態度に、これでよいのかという疑問が湧くのである。この態度からは、文化の創造と発展は見つけ難いものでなかろうか。編集子をさびしがらせた一つである。<後略>
平野:先ほどの「ちょうなん」という詩を巻頭詩に取り上げたことの意味は、勿論この作品自体に光るものがありますが、もう一つ、生活綴方的というか、先ほどの編集後記に「現実をそのまま割り切った表現に心もとなさを感じる」という指摘がありましたが、こういう作品を取り上げることによって「なぜ」という視点を育てていく切り口になっていく実践の構えが窺えるところにあると思いますね。
先生の幾世橋小学校の体験の中で水谷先生の思い出が特に印象深く残っていらっしゃるそうですので、そのお話をお願いしたいのですが…。
2.ガンテツができた!!
針谷:小学校時代の私はどういう子供だったのかというと、できない子だったんです。3月13日生まれでしたので、4月生まれの子と1年近く差がありますし、母が暢気な人で何も教えないで、自分の名前も書けずに入学したんです。本当について行くのが大変でした。毎日泣いていましたね。泣きながら「あいうえお」を書いていた記憶があるんですが、自分の名前を書けるまでに随分時間がかかりましたし、いろいろ呑み込みが遅くって、大変な思いをしました。鉄棒の尻上がりが一人だけできなくて、夕方遅くまで校庭の鉄棒にぶら下がり、それでも出来なくて泣きながら帰ったこともありました。そういうふうに、出来ないことはものすごく悲しいことなんですよね。やってもやっても出来ない、すごく辛いんですよね。そういう経験が自分の中にあるということは今振り返ると、大事なことだったのかなと思うんですね。いま、職場であの子はグズだなんていいますけれど、その愚図な子だったわけです。今も「グズ」という言葉を聞くとドキッとします。その私を4年から6年生まで担任してくださったのが水谷先生で、この先生は軍人だった先生で、とても厳しい方でしたが、徹底して、どの子も出来るまで教えてくれました。怖いけれど最後まで教えてくれた。で、先生が教えるだけでなくて、出来ますと外で遊んで来いと言って、その間に先生が教えたり、また、できた子がまだ出来ない子に教えさせる。これは先生が意識してやったのか、どうかはわからないんですが、これはすごい教育的なシステムではないかなと思うんですが、生徒同士の関係を作る形でやってくださった。私は自分ができない子だったのですが、何とかそろばんができるようになった時、まだできないガンテツという子がいた。この子は顔が真っ黒で、開拓村から通っていて家が大変貧しい子で、栄養失調のせいかいつも青っ洟をたらしているような子、ちょうど、吉野せいの『洟を垂らした神』に出てくるような小柄な子でした。私は付きっ切りで1時間ぐらいかかって、足し算・引き算を必死になって教えたら、できるようになったんです。今思い出してもその時のものすごく嬉しかった思いがこみ上げてくるくらいなんですね。で、「自分が出来なかったことが出来た」というので嬉しかったという体験と、「できない子が出来るようになった」、それが嬉しいという体験と両方味わえたということはすごく大事なことではないのかと思うんですね。それから、水谷先生は生徒に作文とか俳句なんかをよく書かせました。後ろは阿武隈山脈、前は太平洋の荒波が打ち寄せるというようなところ、山や川、野原、沼などがいっぱいありますから、ちょっと連れてゆき、午前中遊んでくるんです。午後に詩や俳句を書かせる、その中で、乱暴ものの前田武夫君の詩が印象的でした。水谷先生は書かせたらそれをプリントしてみんな配布し、又、感想文を書かせたり言わせたりしていたんです。その詩は、虫に食われた蕗の葉っぱに雨がかかり、その虫食いの葉っぱがかすかに揺れたというような詩だったんですよ。普段ものすごく乱暴なワンパクで裸足で飛び回っているような子でしたから、こんな詩を書くのかと一人で感動していたことを思い出します。戸部輝男君は短歌を作りましてね。秋の山に行ったときにリンドウの花が結構咲いていたんです。私はリンドウが大好きなんですけど。
秋の日にリンドウの花咲きつづけ
プリントを渡されて見たときワーすごいなぁと思いました。すると、先生が「ウンこれはナ、秋の日にむらさきの花咲きつづけの方がいいぞ」っていうんです。私はリンドウの花じゃなきゃいけないと思いましたが、すごく怖い先生だったから黙っちゃったんですが。でも、あのときから50年近くもたつのにまだ思い出すんです。そのときの強烈な感動…そのような感動を水谷教室は作ってくれたということなんですね。
それで、今自分のやっていることを見ますと、なんかそれと同じようなことをやっているんですよ。クラス担任をしていると、行事でも何でも、やった後に必ず書かせているんです。書いたものを必ず印刷して文集みたいなものを作るんですけど、それは感動を自分一人だけでなくてみんなのものにしていく、自分の発見を自分だけのものにしないで、みんなのものにしていく、そういうことを、気がつくと自分がやっているんですね。
平野:私は水谷先生で連想したのが寺子屋のお師匠さんみたいな先生のイメージです。詩や俳句を作らせていることから多分教養人で、軍隊の上官としても部下思いの方だたんじゃないかという印象を受けるんですが、教師の専門教育を受けていないので素朴に自分の信念で実践をなさっていた感じがしますね。ある意味、日本の教育の伝統の中には寺子屋から連綿としてつながっている良質な部分もあるようなことを改めて連想したりしました。でも、やはり水谷先生の実践の中には小学校の教師集団の実践のスタイルというものが強く生きているからこそ、水谷先生の力が発揮されているんじゃないかと思われるんですね。先生の眼で見ると、実際、教師集団全体と水谷先生というのはどういうふうに映っていたんですかね。
針谷:どうでしょうね。当時、子供ですからね。よくは分かりませんが、文集を作っている頃は先生方は一生懸命一つになってやってるなぁとは思えましたね。先生方がちょっとしたところに集まってはすごく討論している姿は結構子どもたちの前で見られましたね。意見をたたかわせている場面が。あの頃の職場はそういう雰囲気だったのではないですかね。
平野:でも、水谷先生に担任してもらったときには「幾世橋の子」はないですよね。だけど、水谷先生はその精神を引き継いでいたということなんですね。
針谷:(今になって思うと)そうだと思います。
平野:その辺はもう少し実態に即して分かると興味深いところなんですが、そのことと関わって、いま、紹介された作品に対する針谷先生の受止め方自体の中にもすごく表れていると思うんですけれども、学校とか教師集団と合わせて、先生の幾世橋の体験にとって大きかったと思われる幾世橋の自然について、のちのち関わってくることでもありますのでもう少し、伺っておきたいのですが。
3.「人遠い子」
針谷:幾世橋の自然についてと自分の子ども時代と関わらせて話をしていきます。父が海軍の仕事に携わっていましたので私は生まれが神奈川県の横須賀の近くだったんです。それがなぜ、幾世橋に来たかといいますと、旧姓西というのですが、西家の土地が幾世橋にあり、終戦になって、父は仕事の関係で東京に残ったのですが、ちょうど農地解放で土地を守らなければというので急遽母は子どもたちをつれて福島に戻らなければならなかったのです。西家の墓を守るためですね。私は母について幾世橋に来て、小学校に入ったわけです。生れたところも海に近い場所で、育ったところも海の近く、18歳のときまで海の側で、しかも山が迫っているという豊かな自然の中で育つことが出来たのは今から思うと、人間としてとても貴重なことだと思います。今の子供たちを見ると一番大事なところを育んでくれる、感情や感性なんかを育んでくれる自然をまわりから奪われてしまっている、そのただ中に生きなければならない現在の子供たちの酷さというのを感じます。それで、私の子供時代というのは途中から幾世橋に入っていったわけですよ。ですから、私は少しは訛があるかもしれないけれど途中からその土地に入っていったので剥がれちゃうんです。私は実家に帰って悲しいのは福島訛でしゃべれないということです。西田敏行がNHKの「じじといた夏」で見事に訛っていましたが彼は生粋の福島県人じゃないですか。だから私はよそ者なので、村の子供たちの中に入るのに引けちゃうところがある。もともと性格がおとなしいのでとても引込み思案で気後れがしちゃったんですね。それでどういうふうにして遊んでいたかといいますと、隣りのお寺のお姉さん達と遊んだり、自分で山に行って草花を摘んだりしてそれだけで充分満たされていましたね。そういう子供であったんです。私は少しコクのあるものが読みたくなると繰り返し読んでいるのが石牟礼道子さんの『椿の海の記』という、小説といっていいのでしょうか、とても不思議な物語です。これは石牟礼道子さんの2歳から5歳位までの幼児期の回想で、まだ汚されていない古き美しき水俣を書き遺したいという気持ちで書かれたものなんです。その中に筆者と思われるミッチンという幼女が出てくるのですが、野山をサルの子みたいに掻き分けて歩いていって草や木と会話する子なんですが、それを「人遠い子」と表現しているところがあるのです。私はどちらかというと草や木や花の中にいた方がいい、だからこの「人遠い子」という言葉は私にも当てはまるかなと読んでいて思いました。
平野:外から来て訛れないというのは僕自身も体験してまして、子供時代からずっと言葉が違うという感覚はつきまとっていました。ぼくの場合は周りに同じような子が沢山いましたから、メッキもつかなかったくらいでしたが。
ご自分のことを「人遠い子」だったとおっしゃっていますが、水谷教室で他の子たちとの出会いとか交流が、後々、開かれていく一つのきっかけになったというわけですね。
針谷:そうですね。他人に対して少し気後れしていたのがプリントされた他の子の作品を読む中で、あっ、あの子がこんなの書くのかと気づいて見方が変わっていく、感動していくということですね。余計それが強かったのかもしれませんね。
4.跡取り教育のはずが…
平野:そういう意味では生活綴方の持つ教育力の一面を感じさせるエピソードですね。そして、それをご自分の体験として持っていらっしゃるということですね。
子供時代について触れていただきましたのでご家庭の教育と関わって次に少し伺っていきたいのですが、跡取りを期待して厳しい躾をなさったお祖母さまと本好きのお母さまの教育というのが非常に対照的なものであったということが印象的でしたのでその辺のお話をお聞かせ願いたいと思います。
針谷:父は東京に残って仕事をしていました。幾世橋には母と私を含めて4人兄弟、と母方の祖母がいたわけなんです。私は草や木、土が好きだったんです。百姓仕事は割りと好きだったんです。4人兄弟の中でも私だけは田植えとか畑の種まきなど手伝う子だったんです。あまりしゃべらない子でしたから黙々とやっていた。兄は早くから外へ出ると宣言していましたから、そんな私に白羽の矢が立ったんですね。で、この祖母というのが小学校の補助教員みたいのをやったことがあったらしく、性格的にもとってもきつい人だった。でも、とてもよい教育をしてもらったと思うのは小学3年のとき、ひよこを10羽預けられて、「これはおまえの仕事だ、卵を産むようになったらそれを売って小遣いにしなさい」といって、金銭出納帳を渡されて、餌代にいくらかかって売れたのがいくらで差引残高いくらというのを書かせて、1週間ごとに点検したんです。雨が降っても雪が積もっても餌さくれは私、鳥小屋から出して遊ばせるのも、糞の始末もみんな任されたんです。鶏が死んで1日中悲しくて仕様がなかったなんて経験もしたのですが、自分で小遣いを稼ぐことや、責任を持って仕事をするということはしっかりうえつけられたと思います。ところが一方で、叱られるときには1時間でも2時間でも正座させられて、子曰く「学んで行わざるは学ばざるにしかず」とか「働かざるものは食うべからず」とかやられました。私はグズでしたからじっと黙って1時間でも2時間でも坐っていましたが、姉と妹は巧みに逃げちゃっていましたね。逆らうと本当に殴るんです。髪の毛を掴んで引きずり回す、暴力を振るう、いまなら児童虐待ですね。(笑い)私だけされたんです。それで、何か言うと引っ叩かれるから言わない子になっちゃったんです。話し言葉が未発達状態に置かれて高校3年まで来てしまった。その代わり自己表現するのにどうしたかと言うと一つは無言の抵抗というのを覚えました。誰に教わったわけでもなく、言わないということが唯一の自己表現ということを身につけていました。
それから、女は本を読むと尻が重くなるからと禁止され、見つかると思いっきり引っ叩かれました。それでも読みたいときは電気の傘に黒い風呂敷をかけて読んでいた。しかし、母親の方は女学校を出してもらっていましたから、私が書いたり読んだりすることが好きだったものですから、町に出たときなどには本を買ってきてくれ、それを繰り返し読んでいました。読むなといわれるとますます読みたくなるでしょ、だから、本を読むようになったのはお祖母ちゃんのお陰(?)(大笑い)かもしれませんね。近所では“おなみ婆さん”はおまわりさんより怖いという評判で、「おなみ婆さんが来るよと言うと泣く子も黙った」という厳しいお祖母ちゃんでした。しかし、そういう厳しい人がいたので、男がいない家庭だったにもかかわらず、村の中でも一目置かれていました。
平野:そうすると、水谷先生といい、お祖母様といい、一つの芯の通った、しかも伝統的な教育が針谷先生の、あくまでも一つのですが(one of themですが)、(受けた教育の)重要な骨格になっているのではないかということを感じますね。お祖母様の「子曰く」式の教育は水谷先生の寺子屋式教育に一脈通ずるところがあると思うし、鶏の飼育による責任を持たせる教育の仕方も経営的視点を持った跡取りを育てるための計画的な教育と言えるかもしれませんね。
それに対してお母さまとの関係を引き続きお話下さい。
針谷:祖母は私を西家の跡取りにしようとしていた。一応先祖代々の墓があって、何反か田んぼと畑があったというくらいで、そんなに土地があったわけではないんですよ。で、高校へは進学しないで、小岩井牧場で修業させるというんです。東京の大学へ行っても、農繁期には夜行で帰って(片道8時間くらいかかった)仕事を手伝っていたくらい私は百姓が好きなんです。でも、そのとき、たかが13,4歳の小娘なんだけれども人に自分の人生を決められるのは厭だと思ったんです。自分は百姓は好きなんだけれども、人に決められた人生を歩むのは厭だと思ったんです。それを言ったらそれこそ引っ叩かれて大変なことになるのは(大笑い)眼に見えていましたから、家出をしようかとも思いましたが、それでどうしたかといいますと、無言の闘いを独りでやりました。母はそれを知らなかったんです。お祖母ちゃんに対しては3ヶ月間一切口を利きませんでした。そうしたら、だんだん弱くなって、ついに兜を脱いで、跡取りは諦めたらしく、仏壇の前でご先祖様に報告をする儀式みたいのをしているみたいでしたね。それで何とか高校へ進学しましたが、今振り返ると、あの時小岩井牧場に行っていた方が良かったかな(爆笑)…。
平野:小岩井牧場はその頃から有名だったのですか。
針谷:そのようでしたね、祖母が知っていたのですから。少し後悔もあるんです…。
平野:小岩井牧場といえば日本を代表する独特の牧畜経営の新しい路線を切り開いていったところですからね。
針谷:そうです。岩手県の、あの宮沢賢治が生きた。
平野:お祖母さまは先見の明があった…。
針谷:そう、先見の明があった(笑い)。そっちの方が良かったんじゃないか、それで、あんまり人に逆らってはいけない(大笑い)と。それで一応高校へ進学は出来たのです。高校からどうするかという時に、大学進学を決めました。それはどうしてかと言うと、父は東京で事業を起こしていて、婿養子、母は西家の直系で墓を死守、そこに譲れないものがあったのかもしれません、私が小学5年生のとき離婚したんです。それで、養育費とか教育費は父から出ていたのですが、生活費を貰う時の母の態度に何か卑屈なものを感じていたのです。いつも父親のご機嫌を伺いながら生活費を貰うという生活でした。時には生活費が入らないこともあるらしく、子供にはそれが分かるんですね、最近あれを買わなくなった、何ということでなんとなく分かるんですよ。子供は敏感ですからね。一人で気を揉んでいたこともあったし、父に催促の手紙を出そうとして母に止められたこともありました。それで、何で悪いことをしていない母親が卑屈になるんだろうかと思っていました。ですから、自分の言いたいことを言うためには女性も働ける仕事を持って経済的に自立しないといけないんじゃないか、と思ったのです。それで、自分が一生働くには大学を卒業して資格を取って就職しなければならないだろうと思いまして、大学進学を決めました。高校時代は色々なことはしていたのですが、幾世橋小のような感動は経験せずに終わってしまいました。ただ、福島県は群馬県と同じく戦後も男女別学だったのですが、私の通った双葉高校だけはなぜか、福島県の中で1校だけ共学校だったんです。旧制の双葉中学に女子が入る形になっていましたから、女子の数は少なかったのですが、結構大きな顔をしていました。だから、女子が男子に劣るなんてことは全く考えずに高校時代を送ることが出来ました。
大学で私に最も影響を与えたのはサークル活動でした。地域の子供会に出て行って一緒に勉強したり、遊んだりしていました。地域は茗荷谷・小石川・護国寺あたりでしかね。週一位で子供会が開かれるのですが、1学年年4,5人の担当で計画を立て、終わった後に必ず全学年の担当者で反省会を持ち、全員が発言させられるんですよ。うまく言えなくてちらっと笑ったりすると笑ってごまかすな、なんていわれて(笑い)、何しろ話すのが苦手でしたから、きつかったですね。でもそれが2年3年と続くとだんだん自分の考えをまとめて話すことが出来るようになっていました。やはり、話すことも訓練によって育てられるということですね。これが学んだことの第一です。それから二つ目は両親の離婚、当時は離婚はすごく少なかったですから特別の家庭ですよね、友達と親しくなると、そこまでしゃべらないといけないかな、と思っていたので、親しくなっても、自分の一番痛い部分はしゃべらないようにしたんですよ。だから近寄ってくる友達はある程度親しくはしていたのだけれど、あれ、この人どういう人、分かんない人だったと高校時代の友達は言いますね。そうやって自分の一番痛いところ、辛いところを石みたいに自分のなかに抱え込んでいたわけですが、そのサークル活動の中で、すごく優しい先輩がいて、「あっ、この人なら何でも話せる、これを話したから私のことをダメだとか馬鹿にしたりとかそういうふうにはしない人だな」と思ったんです。2年生の10月の合宿のときに初めてそのことをその先輩に話してみました。自分が一番拘っていたことを話すというのは一人に話せればそれでいいのですね。一人に話せるとそこから扉が開いて世界につながっていく、たった一人に話すことの重要性がその人間にとって如何に大事か、その人間が次のステージに進んでいくためにどんなに大事かということを学びました。もう一つは反省会の中で、誰ちゃんがこんなことを言ってたよ、この前こんなふうだったけど今日はこうなったよ、というように一人一人のことをうんと丁寧に見ていくんですよ。最初はボーとしていて分からないのですが、先輩がそれをやってくれるのでだんだん見方などを教わっていったんですね。その中でも、特にすごく腕白な子でもその子の良いところを先輩達はみようとしていたんです。そのことが、教師になってみて、少しは子どもの良いところを見ようとするのは、子供会サークルのときにちょっとは身についたものかなと思いましたね。ちょっとですよ、本当には身についていなかったことが現場に出たら証明されました。(笑い)現場はそんなに簡単なものではなかったですね。
平野:いまチラッと子供会の体験と教師という職業とのつながりが出されましたが、間を埋める意味で、教師に向かうプロセスの補っておきたい部分があるのですが、進学と関わって、植物の研究がしたいというお気持ちがあったやに伺っているのですが、それはなぜ断念したのですか。
針谷:植物学をやりたいと思ったのは高2のときだったと思います。実は私の曽祖父は漢学者だったのですが、魚屋で魚を買うときにいちいち鰯の頭にお金をのせていってお金を払ったというエピソードの持ち主で、算数にまるで弱い人だった。その系統を引いてしまったらしく、理数系が苦手。人並みの努力はしましたから代数は何とかなったのですが、ひらめきの必要な幾何はダメでした。それで、物理の単位は先生が大きな荷物を抱えて教室に入ってくるときさっとドアを開けてあげて、それでもらったとしか思えない。(笑い)植物は理系ですからそこでダメだったことと、父に相談したときに「そんなもの女のやることではない」と一喝され、止めました。やはり自分が文系の頭だったのが一番でしょうね。
平野:でも、植物の名前を一度見ると分かる特技があると…。
針谷:そういう感覚は今でもありますね。今染色や織物を趣味にしていますが、これが小鮒草、これが茜と教わると、車を運転していても眼の端に入ってくるんですよ。
育った環境の影響なんですかね。
平野:進路選択のとき、小説家になるか教師になるかお迷いになったとか。
針谷:なるんだったら現実的には教師かな、とは思っていたのですが、友人達には出版社に行く人もいたりして、でも、話すことが苦手な私は、書くことで自己表現をしてきましたから、両親の問題もありましたから、人間の抱える不条理な生というものを書いてみたいな、という気持ちはありましたね。現実的に考えれば、職業の中では女性が働く条件や権利が一番確立しているのが教師であったということですね。
平野:発表はしていないが、密かに書き溜めた作品のようなものはあるのですか。
針谷:小説ではなくて、現場に入って、教師としての力も未熟で、自分が教壇に立つためにはそれなりの葛藤があり、その中で、生徒とぶつかり、生徒たちに教えられて作り出した生きたドラマは小説よりもっと面白く魅力的なドラマでした。それを書かずにはいられなくて書いたものが学事出版社からでている「月刊HR」やその他の雑誌に発表されています。自分と生徒たちが作ってきたドラマを書いてきたのは私にとっては財産になっています。
平野:これからそれを小説になさるということがあるかもしれませんね。ここで休憩をいただき、教員になってからのお話は後半に伺いたいと思います。では、ご質問などありましたらお願いします。
司会:質問ご意見等ありましたら、遠慮なくどうぞ。
質問:土地を守るために別居して帰郷したという話がありましたが、どの程度の農業規模だったのですか。
針谷:そんなにないんですよ。田畑は大したことないですよ。家は裏に山を背負っていましたから、山林が何町かありましたけど。(今考えてみますと)祖母がなぜ百姓にこだわったかといいますと、戦時中に食糧難で困ったでしょ、米を作っていれば食うだけは出来る、それでこだわったと思うんです。だから、土地があるなしの問題ではなかった気がしています。それと、先祖代々の墓を守るという意識が祖母や母には私の想像出来ないぐらい強かったですね。
質問:その大学を選んだ理由はなんだったんですか。
針谷:出来るだけ金のかからないところが一番というので国立に。国文は自分としては得意の方だったし、平安の女流文学を読んだときに、母親の生き方が重なりましてね。(母の場合は)男性の動きにものすごく左右されて、気持ちや、経済的にも不安定で、私の目からは理解しきれない不条理に充ちているように見えました。そういう母の生活を重ね合わせながら平安時代の女性の日記や物語などを読んでいましたので、それでそっちの方に行ったのかもしれません。
平野:それは一貫性があるように思えますけどね。水谷先生やお祖母さまの教育もありますし、曾祖父が漢学者であったとか、平安の女流文学に興味を持ったというような針谷先生のライフヒストリーを伺っていますと必然的に国文学を選ぶことにつながっていったように思えます。
質問:針谷さんがお祖母さんに押しつぶされなかったのはどうしてか。
針谷:どうしてでしょう。母とか姉に言わせると、お祖母ちゃんと私がぶつかったのは両方ともよく似ていたからではないか、というんですよ。お祖母ちゃんは「わぁー」と外へ出すんですよ、反対に私は外へ出せないから、黙っている、無口な子でした。だから近所の人はおとなしい子だったというのですが、何もいわないから何も考えていないかと言うとそうではなくて、弱いかと言うとそんなことはない。それだけ抵抗心が強いかもしれない。(大笑い)耐性菌というのがあるじゃないですか。だんだん抵抗力が強くなって抗生物質が効かなくなる(爆笑)…。
平野:お祖母様の厳しさというのも期待が強いが故の厳しさですから、どこかで相通ずるところがあったのではないですか。
針谷:いやぁ、カァと感情的になり、それはすごかったですよ。私は鈍感でそれほどではなかったのですが、母や隣りの小母さんはお祖母ちゃんに私がいじめられていたと言っていましたよ。私はいじめられている感覚はなかったですね、自分がグズだから怒られると思っていました。でも、進路についてはどうしても納得が出来ないので先ほどいったように頑張りました。
質問:「幾世橋の子」を見せてもらってとても感動しているのですが、当時、それを子どもたちにどういうふうに返したのですか。
針谷:これは一人一人配られて、家に持って帰って親子で読んでいましたね。〔追加〕私の小学3年くらいまでは「朗読」の時間というのがあって、夕方6時前になると、「朗読の時間ですよ」と担当の子どもが大声で触れて廻るんです。すると、どの家庭でも、30分間子どもが朗読をする。その時は何を読んでもいいんですが、お母さんは台所なんかしながらそれを聞いている。そんな指導が学校でされていたんです。だから、その時間は村中の子ども達が朗読をして家中みんなでそれを聞いていました。
平野:教材として使うことは?
針谷:それはありませんでしたが、小さな村ですからみんな顔見知りでしょ。みんな読んでましたね。
意見:(想像で申し上げるんですが)お祖母さんと孫の関係ですよね。だからよかった。これが母と子だったら恐るべき鬼母(爆笑)、母と子ならかなりきついでしょう。
針谷:逃げ場がなくなってしまう。
意見:先ほどの(お祖母さんに)つぶされなかったのはお祖母さんだからですよ。現在問題になっているのは母子問題でしょう。
針谷:有難うございます。そうなんです。お祖母ちゃんがそういう人だったけれど母が優しい人で包容力があったので、私が部屋の片隅でしくしく泣いているとしっかり守り、受け止めていてくれた。逃げ場があったので何とかぐれずに(大笑い)済んだといえるかもしれないですよね。
意見:だから、虐待と受け止めずに済んだ。おそらく母だったら多分、虐待でしょう。
針谷:そうですね。母親が受け止める役割をしてくれたんで何とか乗り越えられたんでしょう。
意見:お祖母さんが父親代わりで頑張っていてくれた。
針谷:そうですね。父親代わりをやってくれたんで母は安心して母親役が出来たんでしょうね。両方をやるのはきついですよね。
いまは両方やんなきゃならないお母さんが増えていますよね。きついですよ。離婚しても…、していなくてもね。(笑い)
質問:作文に「だいすきなおばあちゃん」というのを書いていますね。これは「本当のことを書きなさい」という指導に従って書いたのかな。(大笑い)
針谷:いや、私も読み直して、「だいすきなおばあちゃん」って書いているでしょ。あれ!私こんなの書いたのかな、(大爆笑)信じられない。でも、これは小学校2年生でしょ。その頃は素直な子でしたからそう思って書いていたかもしれませんね。本読むな、ビシビシは3年以降ですもんね。まだ2年だからコレ(爆笑)はなかったんでしょう。
*******************
<休 憩>
*******************
5.「生徒じゃなく、針谷先生が
おかしんじゃないの?」
平野:後半は教師になってからのことを中心に伺っていきますが、書いて自己表現することは得意だけれども、言葉で個人的なコミュニケーションをとるのに苦手意識を持っていらっしゃったということで、ある意味、教壇に立つものにとっては致命的な弱点でもあるわけなんですが、その辺りのことから伺っていきたいと思うのですが。
針谷:お知らせのプロフィールで幾世橋小入学とあって卒業を落としてしまったのですが、(笑い)中学から大学までを飛ばして、市立太田商業、藤女、中央、高崎商業高校としましたのは、自分にとっての学校は第1は幾世橋小学校、第2は自分が教師をしている現場、それが私にとっての学校なんだということを、いまものすごく感じているので、あえてそうさせてもらいました。昭和42年4月に教師になったのですが、3年で移りまして、藤女に15年(‘70~‘85年)いました。結婚が早くて、子どもも早くできて、そして、主人が…夫といった方がいいのですか、長男教育がびっしりされていて、親の面倒を見るのが当たり前、母親も家に入るのが当然というところがあって、私は…、どういえばいいのでしょう…、終いには従っちゃったんですね。(大笑い)あのォ、やはり、未熟なんですねぇ。(爆笑)最後まで頑張れない!?最後になるとグズグズグズといっちゃうところがあるんじゃないかと思うんですが…。(笑い)それで、親との同居が始まり、嫁の立場になって突然、縦関係の、封建的な人間関係の中に身を置くことになりました。義母は嫁だから、女だから当然こうすべきだとという考えの人でしたからとても大変でした。教師としてはこれから経験を積み重ねていくときに子育て、家事に時間をとられるから家のことも中途半端で子育ても中途半端、仕事も中途半端、寝る時間もそんなにはない、このまま仕事を続けるかどうか悩みました。藤女の女の先輩先生には愚痴をこぼしたり、聞いてもらったりして助けてもらいました。その中で一番支えられたなと思うのは組合の女性部の学習会でしたね。このまま仕事を続けていいのだろうかと必死に長女をおんぶしながら、オムツを取り替えながら参加していましたが、特に島津千登世さんの学習会で自分なりに掴んでいったことは、「その矛盾を生き抜いていく中で新しい歴史が創られていくんだ」というそのことだけは掴めたような気がしました。中途半端で、これでいいのかと思いながらやっているんだけれども、でも、もうちょっと続けてみたら何か見えてくることがあるかもしれない、と思って何度も踏みとどまって、何とか続けてきました。そのときに一番支えになってくれたのは夫ですといいたいのですが(大爆笑)ここにいないから、いると可哀そうで言えないけれど(大爆笑)夫と言えないところが少し残念なんですが、婦人部(現女性部)の自分と同じ問題を抱えて働いている女性によって支えられたということです。(爆笑)藤女に移りまして、家の近くになり、これで自分なりに仕事の方にも時間が割けるなと思って(太田までは往復4時間かかった)頑張ろうと思ってやってきたのですが、そして、行事など結構楽しくやってきたのですが、藤女10年目、担任をしてたのですが、一所懸命やればやるほど次から次へ生徒が問題を起こしてしまうのです。退学者が二人。生徒のため一所懸命頑張ってると思っているのにそうなんです。そしたら、生徒の一人が、「先生、あんまりいろいろやりすぎるからじゃない」と言ったんです。そうか、でも、私には分かりませんでした。私は生徒のことを考えて頑張っているのに何で生徒は分かってくれない、そういう気持ちでした。それで、3学期になりましたら、もう朝、起きられなくなっていました。起きても吐いてしまうんです。学校に行けなくなっちゃったんです。それでどうしてよいか分からない状態に陥りました。ある先輩に話したら「それは生徒がおかしいのではなく、針谷さんの方がおかしいんじゃないの?」と言われました。で、私はそんなことは一度も考えたことはありませんでしたし、自分は結構いいことをやっていると思い込んでいましたから、すごくショックでしたね。それで、もう一度振り返ってみていったときに、自分がああやりたい、こうやりたいと思うことが優先していて、例えば中間や期末テストではみんな何点以上とろうね、とか、行事はみんなで頑張ろうとか、やってたんですね。でも、まてよ、もしかしたら自分がいいことだと思っていたことが間違っているかもしれないと思い、もう一度見直していったんです。この状態では生徒の前には立てない、と思って休みました。3日間かけて「学級通信」を書いていました。もう一度自分のやってきたことを振り返って、書きました。自分が間違っていたのじゃないのか、という内容のことでしたね。書き上げてやっと教室へ戻れると思いました。それが2年生の時でしたね。持ち上げれば3年の担任になれるのだけれど、私は今の自分のこの状態ではとても3年の担任はできないと思ったんです。その前に自分にとってやることがある、本当に自分のやったことのどこに問題があるか、どう変えていかなければならないか、この1年間かけてみんなに教えてもらって掴まなければならないと思ったんです。先生方は「針谷さん、ここで担任を降りると生徒がいろいろ云うから我慢して続けてやった方がいいよ」と言ってくれたんですが、降りました。その降りた1年間でやったことは、思い出す限りの生徒とのやり取りを、こういうところで私がこう言ったら、生徒がこう言って、こうやったというのを全部、なるべく正確に書きました。そして、高教組の教研に持っていき叩いてもらいました。そしたら、いろいろ出ましたよ。私がその討論で掴んだのは、私は生徒をありのままの生徒として見ていなかったんだなぁということでした。学校の方針もありますから、「赤点とらないようにしよう」「制服、頭髪をきちんとしよう」とか、それをいかに守らせるか、いかに達成させるか、そのことばかりに眼が行って、そういう「学校の、教師としての物差し」でしかその子を見ていなかったから、生徒の一点しか見ていなかった。ちゃんとやる子は良い子、やらない子はダメな子だ、欽ちゃんの昔のTVに「良い子・悪い子・普通の子」というのがあったが、あの普通の子が私にはいなかった。悪い子だと見られている子は面白くないから反発しますよね。
6.「吊りあがった目」
 2学期の終わりの頃にカンニング事件が起こった。教室を点検していて、後ろの黒板を見たら「吊り上った目」の悪戯書きがあり、「最近の先生の目ってこういう目してるよ」って添え書きがあり、「壁に耳あり、カーテンに目あり」とも書いてある。つまり、先生にチクル子がいるから気をつけなって云う意味ですね。それを見て私は愕然としました。
2学期の終わりの頃にカンニング事件が起こった。教室を点検していて、後ろの黒板を見たら「吊り上った目」の悪戯書きがあり、「最近の先生の目ってこういう目してるよ」って添え書きがあり、「壁に耳あり、カーテンに目あり」とも書いてある。つまり、先生にチクル子がいるから気をつけなって云う意味ですね。それを見て私は愕然としました。
自分が学校側・教師としての視点しか持ってなくて、一面的にしか生徒を見ていない、生徒そのものを見ようとしなかった、ということなんです。では、それを変えるにはどうすればいいか、それには、一つの見方でぱっと見てぱっと決め付けるのではなく、まず「なぜ」って考えてみる。なぜその子はそういうことをするのかな、なぜそういうふうに言うのかな、なぜって先ず考える。ある先輩の人が「自分だったらなぜって考えるんだけどー」と言ってくれたんです。私にはその「なぜ何々をするのか」という発想が決定的に欠落していたんだということにやっと気づいたんですね。そして、生徒がいろいろなことをしたときに「なぜ」って考えるようになるまでに5年を要しました。やはり、意識していないとつい、癖が出てぱっと判断してぱっとやってしまっている。そのぱっと思ったときに、次に、「待てよ、なぜ?って考えるんだよ」と自分に言い聞かせて、納得いったらそれから行動、それを繰り返しているうちに、いまはすぐ「なぜかな」というのが自然に出てくるようになりましたね。やはりそれも訓練なんだと思うんです。それでやっと1年がかりでそれらのことを掴みました。
また、大事だと思うことは、問題を抱えたときに私の場合はそれを一緒になってかなり厳しく分析してくれる先生たちに恵まれていたこと、そういう人たちを求めて自分の問題点を隠さず出していったことです。その一つは高教組の教研だし、民間教育団体の「高校生活指導研究会」(略称「高生研」)だったんです。そういう研究会で私は助かった。これがなければ私は続けられなかったか、病気になっていたかもしれませんね。
7.「話すということ」
このように自分の課題を掴んでいく中で、私は自分自身の人と関わる能力についても改めて見直していきました。全体の中での話は出来るんだけど、掃除のときなど教室で生徒と一対一で向き合うときがあるでしょ。或いは生徒の集団の中に身をおいたときにすごく緊張しちゃって、何を話したらいいか、どう動いたらいいか、とか、うまくコミュニケーションが取れない、自然に振舞えないんですね。そういうところが自分にある。何かあったときに生徒と正面から向き合って、自然にそこに入っていく、関わっていくこと、それが自分には出来ていなかったし、そういう力を小学校からずっと育てられてこなかった、自分も避けてきてしまった、ということに気づいたんです。まず、家庭では押さえられていたし、あの幾世橋小でさえ、話す力を育てることが意識的に教育されていたのか、と問うてみるとそれほどなかったように思える。それは私だけでなく、学校教育の中で、小・中・高と意識的にはそういう力を育てる教育はなされてこなかったんじゃないだろうかと私は思ったわけです。それで目の前の生徒たちを見たときにやはり威勢良くおしゃべりはしているけれど本当に一人ひとりと向き合って話していない子が多いのではないだろうか、ということに気がついたのです。気がつく過程にはいろいろあったのですが、その中でも、竹内敏晴さんの影響が大きかったと思います。竹内さんの『言葉が劈かれるとき』(思想の科学社)と「話すということ」を読む中で、竹内さんの経験と私の経験が重なり合い、目の前の生徒たちも他者と本当に向き合って話す力、本当に自分の言いたいことを言う力が育てられてこなかったんだなと感じました。それで、授業の中で、自分が生徒に本当の力をつけるために今やらなければならないことは、やはりこの「話すということ」の授業だろう、「話す力」を育てるということは「人と関わる力」を育てるということで、ただ単に上手な話し方を教えるということではないのだ、そのために単元を設定してやろうと決心したのです。これは当時の藤女だから出来たことです。教科担任が授業計画を自由に組み立てられたのです。それで単元を設定しました。でも、躊躇いはありました。国語の授業で「話すということ」を単元化して授業をする人は周りにはいなかったし、全国的に見てもあまりもいなかったと思うんですよ。でも私は、自分自身の必要性と目の前にいる生徒の課題を考えたとき、それを今、やらなきゃなんないと思っちゃった。でもそれでも迷いましたよ。迷った私の背中を押してくれたのが大村はまさんでした。いま、92歳でまだ活躍していますね。今年の1月に実際にお会いし、握手してきました。(笑い)大村はまさんの『国語教室の実際』(共文社)の中に、「しっかりとした話し合いがされないところに、また、自分の心の通りにものをいうことが出来ない人が大勢いるところに、また、いうべきことをいわない人がたくさんいる社会に、どうして民主国家が成立するでしょうか」こう書いてあったんですね。それを読んだ時に、戦後民主主義になったといったってそれはまだまだ言葉の上のことだけかもしれない。そういう力を学校教育の中でつけていくということをしなくちゃなんないんだな、と思い、それこそ清水の舞台から飛び降りるつもりで、始めました。何しろ怖くてしょうがないんですよ。初めての実践に踏み出すときには、誰も助けてくれないわけですから。自分の頭で考え、組み立てなければならないんですからね。でもやはり思い切って踏み出しました。そして「話すということ」の単元は9月から11月の3ヶ月続きました。
で、12月に初めにまとめのノートを作りましたら1冊の本になっていました。プリント類や自分の書いたことをまとめて本にするのは大村はまさんの実践の中から学んだんですが、生徒一人一人が自分だけの本を最後に作り上げました。このことについては学事出版の「月刊HR」(1983年10・11月号)に掲載されました。
「話すということ」のねらいは上手に話すとか、うまくまとめて話すとかではなく、話すということは、人とちゃんと向き合って働きかけていく行為だからそれが出来ているかどうか見直すこと、また、どのような状態が本当に語りかけていることになるのか=「語りかけが成立する要件」について体験することを中心に置きました。
そこで、最初は発声練習から始めました。大会議室へ連れて行き、「思いっきり声をだせっ!」といってアーと叫んでみたり、発声の練習や体操をしたり、語りかけのレッスン、試験官・受験生の役割分担をした模擬面接(就職の練習を兼ねて)、それらを実践したら必ず書く、書いたものはプリントにして配布、それに基づく話し合い、その話し合いの中で、最後に、どうして声が出ないのだろうね、どうして話せないのだろうね、そういう問題に生徒たちは行き当たった。その時少し歴史的視点も入れるべきかなと考え、樋口一葉の『十三夜』を読みました。なぜかと言うと、主人公のお関は物言えぬ状況に追われて生きざるを得ない、それでも我慢して子どものためにまた鬼の家に戻っていくという彼女の姿を読みながら、声が出せなかったり、ものが言えないのは、今だけではないぞ、もっとずっと前から続いてるぞ、そんなことも明らかにしたかったんだけれど、生徒たちはもっと多くのものを掴んで卒業して行ってくれました。彼女たちは「話すこと」の授業は本当に生きるために役立つ力を教えてもらったと云うふうに書いてくれました。
でも、一番変わったのは私かな、と思います。その授業が終わったときに私は生徒一人一人と話すのがすごく楽しくなっていました。生徒の集団に囲まれていても怖いという感じは全くなくなっていて、自然体で生徒の中に立つことが出来るようになっていたのです。この単元を始める時は本当に怖かったんですが、思い切って踏み出して、夢中になってやった実践で、毎時間ごとに次はどうやるか組み立てていきましたから、大変でしたけれども、それと引き換えにいままで自分に欠落していた力を獲得できたのは生徒の力のお陰だと思うんです。そしてその授業をやった翌年に藤女最後の担任を持つことになりました。1年が終わり2年生の担任になった時、私はA子と出会います。A子は親も周りの友達も、勿論担任も拒否する生徒で、ゲームをやっても一人だけ入らない子でした。その子と私とクラスの子たちの関わり、A子は拒否し続け、それでも少しずつ心を開いていって、しかい、私が少し踏み込んだら又拒否されて、途方にくれたらクラスの子たちが今度は出て行ってA子がクラスへ戻る道を作ってくれた。最後はA子が教室に戻ってきて、私の授業を受けたというドラマティックな展開になりました。中央高校へ転勤する私にA子がくれた手紙には「尊敬+感謝今の私から先生への言葉で一番合っている言葉です。」と書かれていました。「A子が覚えた言葉」を書かずにいられなくて『月刊HR』(‘86年)に書きました。
平野:一番のポイントは話す力をつける授業の取り組みが(針谷さんの)教師としての転機となったということですよね。針谷さんが「人遠い子」として育って、ご自分のおっしゃる“話すコミュニケーション能力が未発達”の育ち方をしたことが、ここの転機を非常にドラマティックなものにしているのでちょっと特殊な感じがするかもしれませんが、本物の教師になるプロセスからいうと典型的な体験だったと思うんです。不登校になりそうな体験、自分の実践のどこが間違っていたかという総括・検証、これらには普遍的な要素が含まれていますね。ただ、生徒をありのままに見ていなかったとか、なぜという問いの欠落など、言葉で整理してしまうと一般的なことになってしまうんですが、針谷さんに即して言えばもっと機微に触れた分析が必要なところだろうとは思います。しかし、それをどう体験するかは一人ひとり非常に個性的なのですが、同時に(本物の教師になるために避けて通れない)普遍性も併せ持つので非常に参考になる実践だと感じました。
一方、これを歴史的な系譜から見てみますと、「話すこと」というのは戦後改革の中では読むこと書くことよりも重視された一つの柱だったんです。ところが、学習指導要領で重視された「話すこと・聞くこと」は実践の流行の中で機能主義に歪曲化され機械的なカリキュラムになってしまい、かえって国語力を低下させるという批判さえ招き、衰退を余儀なくされたのです。ですから、それだけ針谷さんの藤女の実践は新たな照射を与えたといえるかもしれませんね。
で、ここでもう一つお伺いしたいのは、高生研では「話す力」は授業より教科外活動ですごく意識していた思うんですが、針谷さん自体はその辺はどう考えていますか。
針谷:それは私のHRへの取り組み自体の変化として現れていますよね。先ほどもお話しましたように、自然体で生徒の中に入っていけるようになったのですから。それに、問題を抱えている生徒に対する視点が全然変わり、まず「聞く」そして「どうしてかな」と考え、関わっていく。だからA子を教室に戻せたと思っています。
平野:生徒指導の行詰りが教科での取り組みとなり、それが生徒指導で生かされたということですね。
先を急いで申し訳ありませんが、中央高校のお話に移らせていただきます。
7.担任団は生徒の応援団
針谷:中央高校(‘85~‘97年)には大変申し訳なく思っているのですが、実は私は転勤したくなかったのです。新任式のとき全校生徒を前にして私はずっと泣いていました。もう1年で卒業させられるのにと藤女に後ろ髪を引かれる思い、もうあの子達の元には戻れないと思うと涙が止まりませんでした。最初の年から担任したのですが、全然燃えませんでした。中央にいって驚いたのは一応共学校なのですが、女の子が少ないんです。女子職員も少なく、トイレを探すのも大変、鏡もちっぽけなものがポツンとあって、一番感じたのが男尊女卑の言葉を口にする男性職員も多くて、女子高から行きましたからびっくりしましたね。女子がいると男が勉強しなくなるから、男子と女子を別クラスにしようというの案が男の先生から出てきて、実際に併学にした時期があるんです。そんなこと、と思っていたのですが、2回目の担任団を組んだとき、その学年の基本方針として男女共学のクラスとすることに決め、実施しました。もっとも、女子の数が少なかったから男子だけのクラスも出来てしまったのですが大体男女半々のクラスとしました。当時中央は進学校でしたが4年制高校(笑い)といわれていまして、在学中は自由を謳歌して、4年目に気合を入れて大学に合格していくというのんびりした自由の校風に満ちた高校でした。自由な校風は良いのですが、もう少し手を入れればこの子たちの力はもっと発揮できるのにと思いながらみていました。でもこの学年(内山学年と呼びます)では、進路実現だけでなく部活動や行事に積極的に参加して、様々な面で人間として伸びていく生徒作りを目指すということ、人間として常に向上心を持って生きていく姿勢を教えていく、4番目に(これは私の思いが強かったのですが)中央のスローガン、開拓者精神、持続する精神をあえて前面に押し出すというものでした。内山学年団は8人の担任と4人の副担任、12名で作られていましたが、会議は副担任を含めて行っていて、副担任が担任をフォローする態勢がとられていました。
今回のことを卒業生に連絡したら、I(旧姓M)さんから“私にとって中央高校とは”というファクスが届きました。中央ではこういう子が育ったという例として紹介したいと思います。この子は2年生から担任したのですが、お姉さんが優秀だったものですから、コンプレックスの強い子で成績も下位で入学してきたんですね。でも、バスケットがうまかった。当時、(女生徒が少なかったせいもあって)女子の部活動は少なく、女子生徒の力を発揮する場が少なかったのです。でも、なければ作っていくんだよ、という中央スピリットをこの子たちは実際にやったんですね。中学のとき女子バスケットをやっていて上手な子が何人かいて、女子バスケット部を作ろうと考えた。それで、顧問を探し、校長に交渉に行ったり、場所の確保と動き始めるんです。それを担任団がバックアップしていく。そういう活動の中で、彼女は高校に入って初めて自分の力が認められ、それが自分の自信になっていった、自分にとって中央は原点になっていると書いています。この子はみんなが普通の4年制大学に進学するのに対し、自分にあった進学先を選びました。自分は身体を動かしている方が好きな人間だから昼間から勉強している普通の大学には合わないタイプ。昼間は働いて夜間大学に行った方がいろいろなタイプの人に出会えるからそこで学ぶ、それを貫いて実現していきました。
彼女は「中学で変化し、高校で進化した」で次のように書いてくれました。
<(前半部略)クラス委員、生徒会役員、運動部のマナージャー、そして部の設立といろいろなことに挑戦した高校時代。端から見たら、どれか一つにしたら?というかもしれません。でも、私は中央高校だったからこそどの事に対しても一生懸命向き合って頑張れたと思います。その結果、多くの仲間、多くの友人にも恵まれました。そして、一つ一つの出来事がいまの私へ進化させる出来事でした。このときこそ私の人生の原点となっています。自分のしたいこと、夢へ向かって進んでいくことの楽しさ、喜び、苦悩、挫折、これから生きていくための大切なことを私は学びました。この頃の私がいたからいまの私がいる。進化した私は、自分を自分らしく見せることが出来る素晴らしい相手とめぐり逢い、幸せに過ごしています。まだまだ進化できるよう今も自分らしく生きています。有難う、中央高校>
もう一つ言いたいのは、2回目の担任後は、家に病人が出てしまい、担任の出来ない状況になってしまいました。で、副担をしながら3回目の学年団に所属していたときに卒業生の答辞作成委員会(これは、中央高校では初めての形でした)で作った答辞なのですが、これを見ますとすごく大事なことが書かれています。
<豊かな個性、よき人柄と共に教育への情熱に溢れていた先生方、人生のよき先輩として相談を持ちかけた先生方はいろいろな独自の形で私たちに刺激を与えた、私たちを引き出す強いパワーがありました。>
これは自画自賛ではなくて、本当にそうだったんだな、教師が人間的に―生徒にとって、ちょっと面白いんじゃないかと思わせるようなのを持って―生徒の前に立っていることが、青年達にとってはすごく大事なことではないかと思います。
中央高校では「卒業生通信」を出しています。卒業して1年目の夏、2年目に出すこともありますが、そのなかにも、同じような生徒の思いが綴られています。筑波大を出て茨城の中学校の教師をしている卒業生から電話があったので「あなたにとって中央高校はどういう高校?」と聞いたら「もう一度入れるんなら中央にする」というんです。「大学の方がいろいろ学べていいんじゃない?」といったら、「大学より濃いものを経験できた、進学だけで追いまくられるんじゃなくて、自分の好きな勉強が出来、いろんな先生がいて自分が知りたいことを聞きにいくと、それに応えてくれるプロフェッショナルな先生がいて、とても面白かったよ」といっていました。それも学校の大事な条件だと思うのです。
平野:先ほどは針谷先生の教師になる転機を感じたのですが、今度は学校づくりの転機というものを感じました。男女共学のクラス作りのような動きと、少ない女子の部活を、なければ作ればいいじゃなきかという形で校是のフロンティアスピリットを活性化するような試みの中で育った生徒が大学時代よりも高校の体験の方が濃かったといえるような高校時代を送ることができたということですが、男女共学によるクラス作りに教師集団を動かした力というのはその時代のどういう条件が可能にしたんでしょうか
針谷:片方には“女子バイキン論”で女子がいると男子が汚染されて勉強しなくなるから隔離政策が必要というグループがありましたが、他方では、男性職員の中にも男女共学が普通だと考えていらっしゃる先生もいたんですよ。私なんかが働きかけたと云うより、転勤などで新しく加わってこられた先生達やその担任団には北村先生とか私のような女性の教員が入っていたということもあったんですかね。学年団で討論して決定したんです。
平野:生徒たちの要求はどうだったんですか。
針谷:前の学年で女子クラスになった生徒たちはすごく反発していましたよ。昼休みなどに校庭に出て、男子クラスの前で踊ったり(大爆笑)挑発的なことをしていましたよ。それは、彼女たちのある種、意思表示だったんでしょうね。
平野:同じ学校に両方いて別クラスというのは不自然と感じる方もいたのでしょうね。針谷:私たちの学年以降はずっと共学の体制が続いたと思います。ただ、制度や言葉としてはあっても現場にいる人間がどういうふうに作るかが基本だと思いますけれど。
今は男女共学が全体の流れとなっており、新設校等では全部共学になっていますね。高商は併学(1から4組が男子、5から8組が女子)だったんですが、最近、教科選択の関係で男女混合にせざるを得なくて、共学になっていったのだと思います。
平野:フロンティアスピリットの難しさというのは、開拓する荒野があるから開拓できるのであって、動くんですよね。だから、後に続く世代がフロンティアスピリットを持つのは難しいということが常につきまとう。ですから、新たなフロンティアというのは常に見つけていかなければならないことだろうと思います。
針谷:私たちのいた中央高校はもう取り潰されたといってもいいと思うんです。年1回、中央高校OB、OGで旅行に行ってるんですが、中央の前をマイクロバスで通ったら屋根瓦の6階建ての新校舎が建っていまして、「まるで倉庫みたいだな、中央倉庫だ」(大笑い)なんて口の悪い先生が言ってましたが、中央中等学校になってしまったんですね。どういうものが出来ていくのかはこれから見なければ分かりませんが、卒業生と話していて、やはり、自分自身でも幾世橋小学校のことがこんなに忘れられなくて、今の私の実践にも深く影響を与え続けているわけですよ。と同じように、あの中央高校であのときに育った子たちは「俺たち、私たちの中央」と思っていますよ。面白い人がいて、心に残ることができて、その体験というのは生きている限り残っていきますよね。そのことが、本当の教育ということになるのかなと感じています。
8.「先生!偉かったね」
「見放さなかったね」
平野:高商(‘97~)で教育相談の担当になられるのはいつごろなんですか。
針谷:3年前ですね。実は私は生徒会を希望していました。その前3年間ほどクラス担任を一回りしましてね、この子たちにはもっとエネルギーが出す場所が欲しい、そうすればもっとエネルギーを出せるはずだと思っていましたので希望したのです。しかし、教育相談は退職した前任者からたってと乞われたこともありますし、保護者にも年配教師の方がいいかなとも思ったもので引き受けました。
クラス担任の時の話をします。
高商に転勤して2年目に1年生の担任をしました。前に話しましたように中央の最後には家庭の事情で担任を出来ませんでしたから、高商ではどうしても担任をしたかったんです。年齢のせいもあったのでしょうか、少し余裕を持って生徒たちを見られるようになっていました。周りから見ると、生徒を上から押さえつけるようにはやらないから、「なに、あの化粧!あの髪!」といろいろ苦情が来るんですよ。先生も大変ね、とか言われちゃってね。私、実は全然大変じゃないんですよね。すごく面白いんですよね。中央の生徒と違ってストレートに感情をぶつけてくるでしょ、内にこもらない子が多くて、バンバン出してくるんですね。それの応対というのは朝のSHRで教壇に立ったところから、先生ああだ、こうだとくるんですね。うるさい!後にしな、なんていうと、フン!フーン!といわなくなっちゃうから、あっそうかい、ウン、ウンと聞いてやるんです。そうすると、あっちこっちで一斉に言っていたのが、だんだん他人がしゃべっているときには黙って順番を待つようになってくるんですね。そういうやり取りがありました。もちろん、大変じゃないといえば嘘になりますよ。家出したり、チーマーに無理矢理入れられたり。卒業した子が色紙にいろいろなことを書いてくれたのですが、その中に家出をしては学校に出てこなくなるのを繰り返していた子がいるのですが、その子は「先生は私を見放さなかった」と書いていました。また、最後まで反抗的な子がいましてね、それは理由がありましてね、高商は服装や頭髪に関してはかなり厳しくチェックしますから、生徒が反発する。しかし、それは健康的だと思うんですよ。その反発をやめない子だったんです。最後にその子がなんて言ったかというと「先生!偉かったね」(大爆笑)。「私がゴチャゴチャいうのに先生はめげないでちゃんと自分の言いたいことを言い続けてくれたもんね」ですって。この子達はこちらを試してるんだな、これでもかこれでもか、この先生、いつ参って弱音を吐くか、いつ見放すか、それとも見放さないか、そんなことを見ているんだなと思いましたね。良かったな、途中で諦めないで、と思います。そういうことを踏まえて、教育相談をしているんです。不登校の生徒が多いんですが、1年目くらいは今までの経験で大体分かったのですが、ところが2年目3年目になると、どうしたものかなという事例が増えてきていますね。かかわり方自体もどうかな、というのが多くなってきましたね。私はカウンセリングなどは勉強したことはないんだけれどでも、ちょっと専門的な勉強もしなければならないか、と思うようになりました。
平野:教育相談が学校の中でどう機能したらよいのか、今でも試行錯誤の段階を抜け出ていないと思うんです。先生は適任だと思うのですが、教育相談と担任との関係などで難しいことがあるのではないですか。
針谷:そう思います。自分の経験でこう接していけばいいかなと思って自分で直接やっていけば一番やりやすいのかもしれませんが、やはりいろいろな先生方との合意を作りながらやっていくのがすごく大変だなとは思います。でも、担任の先生、部活の顧問、生徒指導主事、管理職の教頭とか、学年主任、養護の先生、専門医などと連絡を取りながら進めていったものについてはある程度、結果的にはその子も変わってきたし、学校に復帰できたし、親との関係も出来たし、そういうプラスの方向には進んでますよね。そこが難しいですよね。担任の先生はどうしても自分で解決したいと閉鎖的になりやすいですし、その辺を大事にしながらサポートしていくにはどうしたらよいのか、やはり、人間関係を作る能力を要求される仕事のような感じがします。
9.「先生、学校作れ」
平野:時間も押してきていますが、あと1年でご退職というところまで来ていますが、卒業生の一人が「先生学校を作れ」といったそうですね。その辺りと今後のことを絡めてお話下さい。
針谷:担任した高商の卒業生が集まったときに、退職したら何するの、って云うんですよ。ウーン、私は好きなことするよ、って言ったら、「先生、学校作れ」っていうんですね。「校長になれ」って云うんです。(笑い)そして、「問題のある子を立ち直らせて」と言うんです。オレたちが先生になってやるよ、って。大笑いしたんです。そしたら順子の学校だから「順校」だなぁ。みんなで大笑いしちゃった。そのときは笑い飛ばしてきたんですが、いま、何で彼女たちはそんなことをいったのかな、と考えるようになった。私が想像すると「先生は見捨てなかったね」その言葉が一つの鍵かなと思うんですね。子供たち自身もどうやっていいかわかんない状態ってあるでしょ。家出しちゃって、戻ってきてもどうしようもないし、どうしたらいいんだろう、という子でも、最後まで目を向けていてくれる大人が欲しいと思っているんですよ。私は中央時代と比較してみると、一人の大人としてこの子たちの前に立っているという意識が非常に強かったことを発見しました。例えば、高商祭参加について討論したときに生徒の方で要求を出したのを学校側はことごとく拒否したんです。それに対して生徒たちはものすごく怒ったんです。先生たちは何で一つも聞いてくれないんだ!って泣き出すわけですよ。すごいエネルギーですよ。私は生徒会長(女子)に最後まで諦めないで本当に1ミリでもいいから前回やらなかった企画を提案してやろうと言ったんです。そのとき、私は生徒指導部の会議で、どんなことがあっても生徒の意見を通さなければ生徒に見捨てられると思ったんですよ。ここで頑張んなきゃ、だから、すごく頑張りました。その提案はオープニングセレモニーで店舗紹介を30分やるだけのものなんですよ。生徒が夏休み中かけて提案してきたものを全部拒否。あまりにも可哀そうでやる気をなくさせてしまう、この位は認めてやらなければいけないんじゃないか、と粘りました。そうしたら、だんだん、まぁやらせてみるか、と云う声も出始め、少しづつ変化していった。そしたら生徒会の顧問がそういうのをやるんなら誰か替わって下さいなんていったのですが、結局最後はまとまりまして、店舗紹介を認めることになりました。生徒が全部仕切って、生徒会の主顧問の先生もやるとなったら本当によくやってくれて、大成功で校長先生をはじめいろいろな先生が褒めてくださったんです。結果はそうだったんですが、そうなる前にウチのクラス討論をやったときにワアワア泣きながら、何で先生は全部ダメって言うんだ、こんなんだったらいいや、どうせ中学の同級生が来てもつまんねよなこんなのは、不貞腐れたようなことを言ったり、そのとき、私はそれじゃ、もうクラス参加は止めろと言ったんです。そんないい加減なことなら止めろ、どんな自分たちがやりたいこととおもってもその十分の一でも出来たらいいという状態が現実の世の中にはあるんだよ、何にも出来ないといって不貞腐れていては何も出来ないだろう。でも、限られた条件の中でも精一杯工夫して力を合わせて何かやれば思いがけない素晴らしいことが出来るんだよ。そういう気がなければもう止めろって挑発したんです。そうしたら生徒たちがワンワン泣き出して、司会の子が収拾に大変だったんです。黙ってほったらかして見ていましたら、文化祭実行委員の子が何事もなかったかのように「それではこのクラスのキャッチフレーズを出してください」と言ったんです。そしたら、今まで泣いていた子たちがいくつか意見を出してきて、店の名前は和風喫茶「じゅん茶」に決まった。(爆笑)生徒たちは私のことを「じゅんちゃん」(私は厭だったんだけれど)と呼んでいたんですね。それに引っ掛けて名づけたのでしょう。それを契機に放課後も残るようになったし、造園業の家から「鹿おどし」を持ってくる子もいて、高商としては大掛かりなものをやったんです。その中でクラスに幾つかのグループもあったけれど、力を合わせていろいろやるのを経験して、クラスの子たちが一つにまとまって何かをやろうということが生れてきたんですね。それで、2月の家庭学習に入ってから、クラス旅行も一泊で企画、自分達で栞も作って、先生たちに企画書を提案してもいいような形でつくってきました。私は強制はいけないぞ、クラス旅行はみんなで楽しむんだから自由参加だぞ、行きたいと思う子が行くんだぞ、とそれだけは押さえなよとだけ言っておいたのですが、40名中30数名参加しましたね。そういうのを経験し、そういう中で育ってきましたから、そういうのが自分の学校というイメージなのかもしれませんね。私は「先生、学校作れ」と言われたことは、自分に何かを求められているんだと感じています。来年の3月で一応学校の教師生活は終わりますけれども、子供たちが大人に要求している、本当に自分達が楽しくて自分達が認められていろんなことが出来る場所、学校を作って欲しいなという要求を受け止めていかなければならないと思っています。まだ、漠然としているのですが、不登校の子と関わっていますと、学校の外側の地域にその子たちの居場所といいますか、力を引き出すような、生きていけるような、楽しんで何かやれるような場所があればと思うんです。幾世橋小学校みたいな学校をいろんな形でいっぱい下から作っていくというのが私の夢と云うか考えていることです。民主主義というのは自分の切羽詰った要求を一人一人が動いていきながらどういうふうに実らせていくか、そこのところから本当の意味で作られるんじゃないかと思うんです。だから、まず、一人が大事なんですね。それから、前々から気になっていることなんですが、群馬に来て最初に疑問に思ったのが「皆様並」という言葉なんです。これ、初めて聞いたんです。実家の方にはない言葉です。職場でも、私の住んでいる地域でも何かと言うと「皆様並でお願いします」と言います。でも基本は、一人ひとりが切羽詰った願いのところから出発していって作るものが本物ではないか、「話すことの授業」も自分自身の内的な切羽詰ったところから出発しましたし、そのことは問題を解決していくときの普遍的なものなのかなと思っています。
平野:幾世橋小学校が原点だという内実が良くわかりました。藤女の話すことの実践にしても、中央の、高商の卒業生の言葉にしても、針谷先生のライフヒストリーの原点であると同時に実践の原点でもある、ということがとてもよく分かりました。どうもありがとうございました。(拍手)
針谷:昨晩この文集を取り出しまして、これを作ってくださった(涙ぐみながら)先生方に話しかけていました。あの、本当に名も無く、そしてそのまま忘れ去られてしまうような存在でも、その人たちが遺したことが、やっぱり、誠実にやっていく中で、それが全部とは言わないけれど、誰かの中に残って伝えられていくのだということを感じています。絶望しないで、100人いたらその内の一人でもいい、と思ってやっていくことではないのかな、と昨日この文集を取り出しながら思いました。この「幾世橋の子」を残してくださった先生方に感謝しています。(感動の拍手)
司会:有難うございました。今日は午後まで部屋を取っておりますので、いろいろお尋ねしたいことを遠慮なく出していただければと思います。
10.“学校体制化” してしまう悩み
意見:先生の前向きなお気持ちに感動しているのですが、一方で、教師は、いい教師であろう思うからなおさらそうなると思うんですが、どうしても学校体制化してしまいますよね。藤女における生徒との確執の中で自分が学校化しているのに気づいたことが先生の転機だったと思うんですよ。ここにいらっしゃる先生方も同じではないかと思うんですが、学校にいるだけで学校体制化してしまうのではないかと思えてしょうがないんです。私は退職してから、あの白い校舎に入っていくのが怖いというか緊張してしまうんです。私はあんなところにいたのか、それって何なんだろうと一緒に考えて見たいと思いました。
感想:「幾世橋の子」の校長先生の創刊の辞と教頭さんの編集後記の二つの文章は非常にレベルの高いもので、それを書かせたのは時代の力ではないかと感じました。針谷先生がご自分の実践を縷々述べてくださいましたが、誤解を恐れずにいえばお二人の思想の地平にはかなわない。先生の実践が意味がない、価値がないと云っているわけではありませんよ。そうではなくて、それだけ時代には想像を超えたすごい力があると云いたかったのが一つです。それから、先の学校体制化についてですが、(私は)教員でないですから外から見ているのですが、針谷先生の話で最も印象に残ったのは吊り上った眼のところですよね。それも本人が気づかない。そういうことはありうることですよ。本来楽しかるべき学校においてそういうあってはならない非人間的関係が平然と存在するという怖さ、それが日常的にあるということは学校を見ていて認めざるを得ないですよね。それは勿論全部ではないし、いいところもいっぱいあるし、いい先生もたくさんいるし、生徒の持っている力はもっとすごいから、それを突っ返す力はあるとは思います。しかし、人は場合によってはそういう非人間的な関係を作り、それに気づかない存在にもなりうるのだ、ということです。水谷先生やお祖母さんの持つ教育力はプロではないが、社会的広がり、深さというか、日常生活から来る強さや視野の広さを備えている。今日の学校教育に必要なのは、学校は社会あっての学校なので、そういう根っこのない学校など何の意味もないから、学校は社会や地域などから養分を吸い上げて生き生きした姿を取り戻して欲しいということを痛切に感じました。
感想:今日は針谷先生が校長ならもう一度教員になってもいいかな、と思いました(大爆笑)。しかし、旦那を大事にしない針谷さんには(私なんか)とても大事にされないだろうと思い留まることにしました(大爆笑)。私が針谷さんの話を聞いていて教員に戻ってもいいと思う根拠は戦後の民主主義はやはり育っているんだと感じたからです。
そういう見方をする人は少なくて、学校は絶望工場だとか、教育は崩壊だとか、教員には希望が持てないとか言われているが、私は希望を持ったですね。教研で針谷さんの模擬授業で指されて答えられなくて、それでいいのかなんて言われて、コンチクショウと思っていたのですが(大爆笑)。私の言いたかったのは、人間であるならばこうあるべきだ、ということを身につけてきているということですよね。これが戦後民主主義の賜物だよね。そこをもう一度反芻したいと思っています。
感想:私は今の先生方は現場でどうになさっているのかなとすごく疑問だったんですよ。だけど今日の話を聞いていて、そして、本気で子どもと付き合っていること、自分の道をきちんと見つけて、たくさん障害や悩みがあったのを同僚や皆さんに打ち明けて、ざっくばらんに自分をさらけ出して、子どもとも本気で対面していったという教育は本当に素晴らしいと思いました。感謝の気持ちを一言述べました。個人的に話したいなということもたくさん生れました。
11.話さなくなった?生徒や教師たち
質問:私は今日始めて参加したんですが、なぜ参加したかと言うと今年TN校へ移ったんですけれど、困っていることがあるんです。私はO校を皮切に、H校、A校と大変な生徒たちの学校にいたんですが、高商と同じようにストレートに私に対して文句や反応が返ってくるところで20何年か教員をやってきて、今年移ったらあまりしゃべらないんですね。今日の針谷さんが「話すことと聞くこと」と国語の授業に取り入れたというのが、あァそうなんだと一番印象に残ったんですが、生徒が話さないだけじゃなくて先生方も話さないんで、何故かなと考えたら、話せないような状況というのがあるように思えるんです。自分の本当に思っていることを正直に話したらちょっと引いちゃうんじゃないかとか、職員会議でもそうですけれども、拙い雰囲気になるんじゃないかとか、バッシングを受けるんじゃないかとか、そういうのが場の雰囲気としてあって、だから今すごく悩んでいるんですね。A校までなら平気でものが言えて、違ってたら何か言われるけれどもそれなりに平気でものが言えたという状況できたところへもってきて今年は少し辛いなと思うんですね。やっぱり自分の思っていることがきちんと言える人が少なくなっている世の中は―さっき大村はまさんがいっているように民主主義ではないというのはホントにその通りで―それが学校の中だけではなくて、社会全体にあるんじゃないか、なんとなくいやだなと思うのです。とくに学校の中は世間よりも強烈だな、と云う気がして、その場に迎合しないと生き残れないような、(或いは)その雰囲気に合わせないとやっていけないとおもわせるような空気があるんじゃないか。それをどうしたら変えられるかということをお聞きしたいと思います。
針谷:学校の雰囲気が居辛いという話ですが、結局、具体的に一緒にやっていく中で意見を出し合っていくことじゃないですかね、先生はまだ先が長そうですから(笑い)。担任団に入っているのと外にいるのとでは学校への関わりが相当違いますよね。中心は学年団なのでそこに入って、具体的に生徒とどう関わるかで意見を交換していって積み上げていく、まずはそのことかなと思います。最初だからとっつきにくかったり言いづらかったりすることはありますよね、私の場合は中央へ行ったときがそうでしたが、最初の学年のときは自分の考えを広げていくことは出来ませんでしたね。二周り目の学年では自分のクラス実践を学年全体へ広げる取り組みをしましたね。一つ一つ具体的にやっていく中で3年間終わったら教師集団の人間関係も少し変わってきたし、生徒自身も変わっていきました。高商のときは全く意見の違う先生もいたし、なかなか意見の交換もしにくかったけれども、それでも1年ごとに生徒の実際の問題にかかわって意見交換をする中で最後は変わってきますね。ですから、具体的に(何かを)やっていく中での意見交換がベースにあるんだというふうに思うんですけれどね。
意見:この3月まで現職で定年退職したんですが、私は職員会議などや自分の所属する場で発言するのはとても大事だなと思っていつもいつも大切にしてきました。で、今に話の中で、周りの人たちと共通点を持ちながらやっていくということが原則だとは思うのですが、そういうものが形成されていないからといって発言を躊躇するというのも自分にとってすごく精神衛生上良くないことなんですね。発言できなかった、発言を回避するのは“沈黙は共犯なり”と云う通り、それに加担してしまうのではないかと思ってきました。だから、空気の冷たさはあるにしても、言わなければいけないことは(自分を貫き通すためにも)発言していかなければと思います。そういう思いで最後まで云うべきことを言ってきつもりです。その中ですごく印象に残っているのは、F校の農業科に勤めていたときのことです。もう30年も前の話ですが、その時代も厳しいことはいっぱいありましたが、女性の先生たちで、一人の人が発言したら必ず他の先生も何でもいいから発言してつなげようと言って、次々に発言していきました。これは特に意思統一したわけではないのですがみんなで実行して孤立しないようにしました。発言した後、誰も何も言っていくれないと淋しいですよね。私はそのことを思い出すと今も胸が熱くなるんですが、次の学校もそういうことで、活発な職員会議が出来ました。私自身もそういう思いを持っていますから、人が発言したときには私で関われることがあったら逃さず発言するようにしてきました。自分が発言しても誰もフォローしてくれなかったこともあるのですが、それはそれでやむをえないことですから、終わったところで自分から仲間に話しかけたりしながらカバーしあえる人間関係を作ることに努めました。最近は、職員会議の議題が事前に知らされないから、根回しも打ち合わせも出来ず虚しい発言に終わることもしばしばですが、言わなかったことが生徒のために良かったんだろうか、教育全般にとって、学校運営上、良かったんだろうかと問い直しながら、それでも時には言えなかったときがあって、残念だったなとか気がつかなくて逃してしまった、とかいっぱいあるんですけれど、自分は出来るだけ避けずに貫き通してきたという思いがあります。
針谷:個人的な面では、すごく言いづらい雰囲気が広がっていますが、その雰囲気を感じて自分の方にも壁を作っちゃってることはないだろうかということをもう一度問いかけてみる必要があるような気もしています。
意見:「幾世橋の子」の創刊号が出たとき、初めて中学の教員になり、職員室の雰囲気等はここに書かれているような雰囲気で、本当にやりがいがあるなという感じでした。職員会議も4時頃から始まって7時くらいまでやってましたね。子どもをどう育てるか、校長を始め真剣に取組んでいました。それが、あの勤評闘争を境に徐々に徐々に変わっていった、そういう教師の経験を経ながらやってきました。私は10年目が終わったときに、高校生の急増対策で高校に移りました。できれば男女のいる高校を希望して移りましたが、ところが全部併学なんですね。最初の高校で4年目に担任になったときに男女共学のクラスを作りました。1,2年持ち上げて3年目に転勤しましたら、そこも併学。そこでも最後の4年間で共学のクラスを作りました。最初の高校へ赴任したとき、バンバン退学させるんですよね。中学には退学はないですからこれには驚き、抵抗しました。次の学校でも退学者が続出しましたが、私のクラスからは一人の退学者も出しませんでした。その学校には12年間いましたが、仏のS先生とあだ名がつきました。そのあと通信制の学校。ここは共学でした。最後は有名な反組合の校長がずっと続けているM商業で7年間やったわけですが、ここでも男女併学でしたので共学化に取組みました。私の担任したクラスは共学ではなかったのですが、彼らを送り出して定年退職になりました。その間、だんだん息苦しさがまして行きましたね。その後何年か非常勤をやりましたが、その傾向は続きましたし、生徒の荒れも目立ち始めました。何とかしなければと思っていたら東京都のあの問題でしょ。娘が教員になりまして、最初は養護学校で、本当に生き生きと生徒と一緒にやっていましたが、去年、普通高校へ移りましたら、今年なんか息苦しいと言っていました。勤務がすごく厳しくなっているし、夏休みにもなかなか休暇が取れない状況の中で大変だと言っています。自分の体験でもそうだし、相当大変な方向へ向かっているという実感があります。昔のような何でもいえる職員会議にしないと(教師が)危ないと思うし、何でも好きなことがいえる学校にしなければということを痛切に感じています。
12.受け入れられる環境が大事
意見:私は今小学校の教員をしていまして、障害がある子の担任をしていますが、高校の先生と話したりすると、先ほども出ましたが、“グズ”という言葉がちょっと引っかかるんですよね。小学校は選別がなくて入ってきますからいろいろな子がいますが、その中には所謂グズと表現すればそれに当たる子もかなりいるかもしれません。能力的には様々なんですけれども、どうしたらその能力を自分でちゃんと発揮できるようになるかというと、周りがちゃんと受け入れることが前提だと思うんですね。結局、グズといわれちゃう子というのは、自分にいい感じを持って、自分の能力を発揮していくところが欠けている子だと思うんです。だから、(能力を発揮するためには)人間そのものがきちんと受け入れられていく環境というのが大事だと思うんです。それは(グズと表現されてしまう子や)子どもだけの世界に限られるのではなく、人間全部を含めてそうだと思うんです。先ほど言われた学校や職員室が硬い雰囲気になっていて、自分を出しにくいというのは、もうちょっと広げて考えれば、その学校の先生一人ひとりがその人なりの能力を発揮していくことにブレーキがかかっていくことにつながっているのではないか、(従って)豊かな学校(創り)にもブレーキがかかってしまうと思うんです。
だから、一人ひとりが認められていくというのは、対子どもだけではなくて世の中全部に関係していることではないかと話を伺いながら思いました。
感想:私は針谷先生より歳は少し下ですが、定年ということを考えると、遣り残していることがたくさんあるので少々慌て始めている状態です。私は山形で生まれ育ちました。北方教育運動、綴方運動の影響の強いところで小・中と随分書かされました。書かされたというと語弊がありますが、むしろ喜んで書いていたと思います。中学2、3年生まで日記を書き、先生が点検していたと思いますが書かされている意識はありませんでした。そういうところが今の生徒たちとの違いかなと思います。山形は『かもしか学園』やら『やまびこ学校』やらの実践のあるところですので、村山俊太郎の子どもと小学校のとき一緒だったよと云う人と同級になったり(大笑い)或いは針谷先生に言った吉野せいさんは私の大好きな人ですし、前半はとても懐かしく聞かせていただきました。現在の私は校内巡視と称して、昼休みいっぱい、学校の中をウロウロしながらできるだけ生徒のホンネというか、生徒の方で言いたいことを言ってきますのでそれを楽しんでいます。しかし、授業を通じてもうちょっとホンネが書けたりするような実践(ちょっと悩んでいるのですが)をやっていこうかなと考えています。
*******************
司会:今朝、新聞を読んでいてニート(NEET)と云う言葉を始めて知りました。皆さんはご存知ですか。ニートというのは働きもしないし学校にも行かない(不就労・不就学)若者と云う意味でなんと52万人を超えた、坂口大臣の話では100万人以上いるだろうというのです。先日の日本教育学会の分科会の様子を「戦後教育史ニュース」の特別号として発行したのは行ってきた事を知らせるのが目的ではなくて、私たちの学習会の欠点というものを見事に指摘されたからです。司会をなさったのが門脇先生(筑波女子大)で、早速、賛助会員になってニュースを読んでくださることになりました。先生は、「社会力」という言葉をお作りになり、その問題を追及なさっているのですが(『子どもの社会力』その他)、『親と子の社会力』(朝日選書)の中で、いまの教育でもっとも欠けているのは「社会力」(註)を育むことではないかという指摘をなさっています。今日、針谷先生のお話しの中にそれに通底するところがあったように思えます。今日は素晴らしいお話を有難うございました。
(註)社会力とは「人が人とつながり社会をつくる力」を意味する門脇氏の造語。社会の運営に積極的にかかわろうとする態度やより良い社会をつくろうとする意欲を含み、より良い社会を構想する能力や構想した社会を実現していける諸々の資質や能力をさす。最近、他人の存在に全く関心を持たず、愛着もない子どもや若者が増えているという。併せて、『「個性」を煽られる子どもたち』(土井隆義著 岩波ブックレット)を読むことをお勧めする。(スタッフ)
13.〔追 録〕
学習会後、3通の文章をいただきました。ご本人の承諾を得て追録させていただきます。(スタッフ)
*会を終えて
自分のことについて話すのは、とても恥ずかしいことですが、しかし、9月11日の会場であのような席に立ったのは、ただ、幾世橋小の先生方のことを語っておきたいという一心からでした。参加者の皆様のご感想やご意見は皆、興味深いものでした。会の終了後、高商時代の教え子がひょっこり現れたのには驚いたり、嬉しかったり。
話し終えて、言い足りないことがアレコレ出てきましたが、その中で二つだけ書いておきます。
◆“グズ”という言葉は、とても侮蔑的な言葉です。私もグズと言われ、グズと自分でも思っていた子でした。けれども、今は、“グズにはグズの強みがあるのだ。しぶとさがあるのだ”と心密かに思うようになりました。
◆戦後民主主義について、群馬の町の片隅で暮らし、学校という場で働いてきて思うのは、今までの日本の民主主義は上州の言葉で言えば、“皆様並”の民主主義ではないかということです。一人ひとりにとってどうしても必要と感じられる“切羽詰った”民主主義=“ひとりひとりの民主主義”は本当にこれから創られていくのだ、いや、もう様々のやり方で創られつつあるのだと思うのです。「地しばり」という草は根っこを地面に張りつかせて、ちょっとやそっとの風には吹き飛ばされません。そんな「地しばり」みたいに、ひとりひとりが、誠実に辛抱強く、自分の大切なものは何かを問い続け、それを発見し、養い育てる営みこそが本物の“ひとりひとりの民主主義”を創っていくのだと自分自身に言い聞かせています。
*「その矢は木にささっていた…」
(針谷先生への手紙より)
前略「幾世橋小学校は教育の原点」を聴かせていただいてありがとうございました。…最後に針谷さんが幾世橋小学校の先生方についての感謝の思いを涙ぐみながら話された時、私も思わず目頭が熱くなりました。ロングフェローと思われる詩に「矢を放った。その矢は飛んでいってしまった。長い時が経って、ある森の中でその矢は木にささっていた…」という内容の詩がありました。その詩は、確か、その針谷さんの言葉にあったように、(「矢」という言葉を用いましたが)「ある人が放った言葉や行動が長い年月たって思いもよらない所で生き続け、光を放っている」という感じなのです。(中略)今週9月16日、いよいよ六十歳になります。私には大した実践もなくて本当に恥ずかしいのですが、あと半年、授業と生徒との係わりを大事にすごそうと思っています。今、二年生の一クラスでR(英語のリーダー)の時間に声がでないのをどうすればいいか悩んでいます。男子13(名)、女子24(名)というクラスで男子が全く声が出ないのです。女子はしっかり者が多く、二年生男子は文系の生徒がおとなしく、自信がもてないのか、なかなか声が出ない。発声練習がいいか、英語の歌がいいか、などあれこれ考えますが、男子クラスだと安心して(?)声が出る。あと半年、たたかい続けて何とか自信をつけたいと願っています。いい知恵があったら教えてください。ダラダラと書き連ねてしまいました。中央高校で良い出会いに恵まれたことを幸せに思っています。
九月十一日 北村友子
*「じゅんちゃんと私」
高崎商業高校卒業生 熊倉由美子
私は高校1年の途中から少し学校を休みがちになり、成績も最後の最後のほうで、なんとなく劣等生っぽくなってしまいました。その時は、ただ、誰もいない家にいるのが本当に嫌で、夜あそびをして、次の日がつらくて学校を無断欠席したり、ちょっと嫌な事があっただけで学校に何も言わず早退したり。その時はあまり気がつかなかったけれど、今思えばじゅんちゃんは自分の親以上に心配してくれて、又、私の事をすごく考えてくれてました。
高商は化粧してはいけなくて、修学旅行に行った時に、みんな化粧しているのに、たまたま私が他のクラスの先生に見つかって、すっごくおこられて、「何で私だけおこられるんだろう」と思ってへこんでいる時、じゅんちゃんが、持っていたハンカチにつばをつけて、何も叱ったりもしないで、私の化粧を落としてくれました。「じゅん、きたないよー」と言いながらすごくうれしかったです。
夏の日に、お弁当にスパサラをつめて学校のお昼ごはんにしたら、食あたりをしてしまって、次の日学校を休んだら、じゅんちゃんが心配してくれたのか、私にお弁当を作って来てくれました。お弁当の中には、手作りのコロッケが入ってました。私の母は朝から夜中まで仕事をしていて、お弁当を作ってくれたことがなかったので、高校に入ってその時が初めてのまともなお弁当で、しかも冷凍ではなくて全て手作りっていうことにとてもうれしくて、そしておいしかったです。本当に感動でした。私の欠席が多く、夜あそびが学校にばれてしまったり、学校やめたいと思ったり、色々が重なって、じゅんちゃんと母と私の三者面談をしました。母がじゅんちゃんの前ですごく私に対して叱りました。私がうつむいていると、じゅんちゃんが「そんなにおこってはいけませんよ」と逆に私の事をかばって、母に対して叱ってくれたのですごいびっくりしました。その日の帰りに、母は担任が順子先生で本当に良かったねぇと言ってました。こんなに思ってくれる人はなかなかいないよと。私もそう思いました。学校をやめずにつづけていったけれど、休みぐせはなおらないまま卒業まぢかになった時、まだ卒業したくない!って本気で思いました。せっかく高商に入ったのに簿記検定もとれず、しかもじゅんちゃんに甘えっぱなし、迷惑かけっぱなしのまま終わってしまうなんて、また1年生からやり直したいと思いました。
卒業生を送る会(註:予餞会)の日、じゅんちゃんは「卒業写真」をうたってくれました。みんな、席からじゅんちゃんのいるステージの前まで出ていき、三年八組のみんながじゅんちゃんの歌に大号泣でした。「じゅんちゃーん。」と言いながら…。
そして卒業式当日、私は最後の最後までじゅんちゃんに迷惑かけてしまったのです。卒業生が胸につける花をさっそくどこかへなくしてしまって「じゅんちゃん花なくしちゃったよー」とあせりながら言うと、じゅんちゃんが自分の胸についている花をはずして私につけてくれました。
じゅんちゃんは誰かが何か失敗したり何かとんでもない事をしてしまっても、ぜったいに責めたり、「まったく…」とあきれたりしません。クラスみんなのきもっ玉母さんでした。みんなは順子先生をじゅんちゃんと呼び、じゅんちゃんはみんなの事を名前で呼んでくれました。卒業してからもクラスのみんなが集まったりするのは、クラスを率いるじゅんちゃんがいたからだと思います。
今年から私はじゅんちゃんに推薦状を書いてもらい、専門学校に行く事が出来ました。高校3年間の後悔した分、今はまじめに学校へ行くことが出来てます。休まず学校に行って、成績も上の方を目指して卒業して、将来有名なトリマーになって、じゅんちゃんが私の教え子だよと自まんできるようになりたいです。そうなる事で、さんざん迷惑かけてしまった事への恩返しできたらと思ってます。
高校三年間、私の担任がじゅんちゃんで良かったです。というより、じゅんちゃんでなくてはダメだったとおもいます。じゅんちゃんは、母があまり家にいなかった私の、第二の母でした。
(スタッフ:熊倉さんは学習会の途中に来らましたが、場違いな感じがして入れなかったそうです。入ってくれていればと残念でたまりませんでした。せめて紙上参加を、の呼びかけに応えて、長文の思い出を書き送ってくれました。有難うございました。) (文責:橋本)