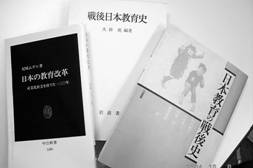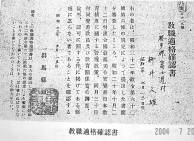市民学習会
第 13 回
戦後教育史学習会ニュース№14
|
戦後教育史を学ぶ
柳井先生のライフヒストリーを聞く
コア連と郷土教育 (抄)
〒371-0026群馬県前橋市大手町3-1-10 教育会館内 ℡&fax027-235-8876
‘04.7.23 群馬県高校教育研究所発行:編集/橋本寛文
|
‘04年7月10日(土)、前橋市総合福祉会館で柳井先生のライフヒストリーを聞く「コア連と郷土教育」というテーマで市民学習会が開催されました。戦時中の師範時代のエピソードの数々、戦後になっても皇国教育は続いた。新教科「社会科」教育の模索と実践の新制富士見中時代。『富士見村誌』を作り、富士見村の全小・中学校 の全教科で取り組んだ「『富士見村 誌』活用計画」の作成とその実践。しかし、教職員組合を労働組合へ変えた「勤評闘争」の代償は大きかった。逮捕され裁判闘争。社会科教育実践の原点、富士見中を追われ、北橘中へ。今井・都丸両先生の指導のもと、郷土教育研究者として教師の情熱と良心を注ぎ込む日々が続く。数々の証言。無罪判決。そして得たものは…。
の全教科で取り組んだ「『富士見村 誌』活用計画」の作成とその実践。しかし、教職員組合を労働組合へ変えた「勤評闘争」の代償は大きかった。逮捕され裁判闘争。社会科教育実践の原点、富士見中を追われ、北橘中へ。今井・都丸両先生の指導のもと、郷土教育研究者として教師の情熱と良心を注ぎ込む日々が続く。数々の証言。無罪判決。そして得たものは…。
先生の真摯な話に誘発されるように、参加者の体験談が相次いだ。
なお、正確を期すため一部加筆・訂正、追録があることをお断りしておきます。
*******************
司会:今回は「教師のライフヒストリーを聞く」の番で、柳井先生をお迎えし、前半は先生の自己形成、後半にそれに関わって「コア・カリキュラム連盟と郷土教育」のお話を伺っていきたいと思います。まず、簡単に柳井先生をご紹介させていただきます。先生は1927(昭2)年富士見村米野に農家のご長男としてお生まれになり、戦争中に群馬県師範学校に入学され、敗戦後の‘48(昭23)年、群馬師範学校本科をご卒業になっておられます。その年、新制富士見中学校で教員生活を始め、北橘中・南雲小・
*******************
橘北小(教頭)・粕川中・杲小(校長)・三原田小を歴任され、‘88(昭63)年母校・原小学校を最後にご退職になられました。その後、群馬県史編纂室の嘱託を勤められ、お手もとにあります「天声人語」で紹介されました『老農船津伝次平』を始め、『群馬の寺子屋』(みやま文庫)『角田柳作先生-アメリカに日本学を育てた上州人』(上毛新聞社)、『師範学校-太平洋戦時下の教育-』((同)『教科書が危ない』入江曜子著岩波新書に引用された)、『新制中学教員の記録』(煥乎堂)他、多数の御著書があります。特に、後二著作から先生に選んでいただいた部分をまとめて、資料としました。先生のお話に合わせてご参照下さい。なお、先生の御著書を何部か置いておきました。貴重な資料が満載されておりますし(“戦後教育史を学ぶ”学習会の内容を裏付ける資料がたくさんある)、特別な価格でお分け願えるとのことですので、ご購入いただければと思います。
平野:それでは始めさせていただきます。前半は、先生の生立ちから師範学校時代についての体験的なお話を伺いたいと思います。お母様が「子どもには学問を身につけさせたい」とのご意志があったと承っておりますが、その辺から…。
1.昭和不況の中で
柳井:柳井久雄です。私は、先ほど紹介されましたように、昭和2年、富士見村米野の農家の長男に生れました。江戸時代は沼田街道米野宿で「中屋」という屋号で和菓子の製造を大きく営んでいたようです。(いまでも)蔵の中には当時の大福帳とか道具等いろんなものが残っています。明治になって農業専門になったのです。私の幼、少年期のことを申し上げますと、昭和初頭の大恐慌の時代でした。特に繭価が大暴落し、(富士見村のような)養蚕村は大打撃を受け、農村は極度に疲弊しました。『群馬県議会百年史』(昭和54年)を編纂するとき、私は昭和前期を担当しましたが、昭和7(1932)年(私の5歳のとき)の県会で、ある議員が、貧困による欠食児童の数は、という質問をしています。県当局は現在給食を要する児童は5,340人いる、と答弁しました。しかし、この数は毎日弁当を持ってこられない児童数で、一日おきとか二日おきの子どもはこの5、6倍にはなったろうといわれています。米をつくる農家でも、真っ黒の麦飯でした。学校に弁当をもってこられない子もいました。教科書が買ってもらえず、古本教科書で学びました。県史編纂室にいるときに「教科書供給表」(文部省)というのを見ましたら、毎年新しい教科書を使うのが何人、古いお下がりを使うのが何人という統計が出ていました。やはり、群馬県は養蚕県でしたから、古本教科書が多く使用されました。上級生から譲ってもらう家が多かったのですね。
しかし、私の母はせめて教科書だけはというので4人兄弟全員に毎年新しい教科書を買ってくれました。一生の思い出の修学旅行にも、貧しくていけない子が多数いました。当時教科書は3銭位でしたが、それでも買ってもらえなかったのです。不況に伴い、昭和5年11月の県会である議員の、中等学校の生徒が不況のため中退していると聞くが何人ぐらいいるか、という質問に、県当局は学費支出困難で退学したもの、昭和2年度32名、3年度47名、4年度53名、と報告しています。不況のため中退者が続出したわけです。当時の人に聞くと、これら中退者は親に気づかれないように布団を被って声を殺して泣いていたそうです。昭和5年12月1日の県会で、ある議員が今日社会の有様を見ると随分困っているけれども、公設質屋へ子どもの着物や鍋釜を持って来て10銭くらい借りていくものもいる、高崎連隊の残飯を1貫目12銭で買い、4人世帯で一日食っているものもいるという発言があります。なお、当時の上毛新聞(昭和6年3月2日)に「生糸の国日本に繰り糸の煙断つ、きょうから全国の製糸工場は休業に入る」とあります。製糸の町前橋の煙突の煙が消えたんですね。
昭和7年、利根郡のある村では、1学級70人児童のうち米の弁当を持ってくるものは僅かに3人だったと記録されています。
昭和7年9月8日に「教員の給料不払い4ヶ月どうして暮らす、農村不況はいよいよ深刻」という見出しが出ています。
しかし、私の母は、40代で母を亡くし、弟二人妹二人を親代わりに育てながら一生懸命農業をしました。資料1頁の最初にありますように母(明治32年生まれで、一昨年104歳で亡くなる)は米野村の女の子でただ一人高等科を終えています。母は婿取りで家業を継いだのでしたが。親が高等科へ出してくれたように、自分の子に教育を付けるのを使命のように思っていたようでした。
また、母は先生をうんと大事にしましたね。
ここにお見えの両角先生は姉の担任をなさってくださったのですが、母は家庭訪問で先生が来てくださることが分かると、汚い農家の広い土間を綺麗に掃除し、水を打たせて、その土地の荒物屋で一番良いお菓子を買ってきてもてなしました。先生を非常に尊敬していたようです。母の教師に対する畏敬の念のようなものが私の子供心に強烈に焼きついています。弟も師範学校に入らせられました。母の云うところでは、農家では人手はいくらあってもよいが、長男を出して、弟を出さないで兄弟不和が起こってはかなわないとのことでした。しかし、弟は理科系だというので新制大学が出来たときに、桐生の工学部の電気科に入ったんですね。工学部に通うためには、米野から田口まで走っていって、そこからチンチン電車で前橋駅まで行って、国鉄の両毛線に乗り換えて桐生駅、そこからまた梅田にある工学部まで走って通ったんですね。そしたらいつの間にか足が強くなって、(『群大工学部百年史』に出ているのですが)北関東の大学陸上競技会でよい成績をとったおかげでマラソンや駅伝の選手となり、前橋・高崎など5市を巡る大学の大会や青森駅伝などに参加、時折優勝したようです。弟(卒業後、朝日新聞に入社)は、息絶え絶えになりながらも走りきりました。なんで体力の限界を超えられたのか、それは結局、提灯を点け、真っ暗なうちから桑摘み、稲刈りをしていた母の働く姿を見て育ったので、「負けてなるものか」という思いが自ずと湧き出し、気力で走ったからなのだと思います。それは(私には)聞かずにも分かるような気がします。私も警察に逮捕されたり、減給されたりと教員として奈落の底まで落ちましたが「こんなで負けてなるものか」と奮起できたのは、それはやはり母への想いからでした。以上です。
平野:お母様自身が学校に行かせて貰った事にとても感謝しておられたとのことでした。(これに関連して)日本の近代教育が成立する前提には江戸時代の寺子屋教育の伝統というものがあるということをイギリスのロナルド=ドーアという教育学者が『江戸時代の教育』に書いていまして、その中で、(近代学校はヨーロッパから移入された制度ですが)江戸時代の町人や農民達の中に学習意欲の高い層がかなり分厚く存在していたということが近代学校への移行をスムースにさせたという指摘があります。いまの先生のお話は正に個人の具体的なレベルで、連綿と伝わる向学心のようなものを引き継いでいらっしゃるということで、それを裏付けるものでした。しかし、そういう向学心のある方たちが、近代的な学校制度の中では決して条件に恵まれていたわけではなかったのが、柳井先生の代になって師範学校へ子ども達を進学させると云う形で実を結んできたということが分かります。その師範学校へ進学した際にお父様が「まるで軍隊の入営のようだった」とおっしゃったということが『師範学校』の中に書いてありました。そのときの様子をお話下さい。
2.皇国教育ノ幹トナラン
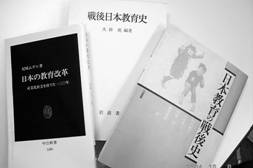
 柳井:私は昭和17年、太平洋戦争が始まってまもなく師範学校に入りました。資料2頁をご覧下さい。写真は、当時の群馬県師範学校の校舎で今でもヒマラヤシーダの木だけは残っています(現、県民会館)。父は「まるで軍隊の入営のようだ」と言いましたが、新入生の「諸注意」を軍事教練の教官が「みんな分かったか」と大声でしているのを聞いたり、寄宿舎の様子をみてそう思ったのだろうと思います。素(そ)絢(けん)寮(註)第16号室の見取り図がありますね。入り口近くが新入生で、新兵、奥が一部(高等科から入学)5年生と二部(中等学校終了後入学)2年生となっていて、いわば古参兵、寝室は2階にありましたが、布団の敷き方もこれと同じ順番でした。1年生は早く起きて火鉢に火を入れたり、上級生の靴を磨くのが日課でした。こういうのは軍隊の内務班とまるっきり同じだったのです。そして、夕方に舎監と寮長が来ると、起立して第16号室総員何名、事故者ゼロ、と報告する。また、「一部1年甲組柳井、誰々に用事があって参りました」「一部1年柳井、誰々に用事が終わって帰ります」なんていうのは軍隊生活の経験のある方は(軍隊と)そっくりだということが分かると思います。
柳井:私は昭和17年、太平洋戦争が始まってまもなく師範学校に入りました。資料2頁をご覧下さい。写真は、当時の群馬県師範学校の校舎で今でもヒマラヤシーダの木だけは残っています(現、県民会館)。父は「まるで軍隊の入営のようだ」と言いましたが、新入生の「諸注意」を軍事教練の教官が「みんな分かったか」と大声でしているのを聞いたり、寄宿舎の様子をみてそう思ったのだろうと思います。素(そ)絢(けん)寮(註)第16号室の見取り図がありますね。入り口近くが新入生で、新兵、奥が一部(高等科から入学)5年生と二部(中等学校終了後入学)2年生となっていて、いわば古参兵、寝室は2階にありましたが、布団の敷き方もこれと同じ順番でした。1年生は早く起きて火鉢に火を入れたり、上級生の靴を磨くのが日課でした。こういうのは軍隊の内務班とまるっきり同じだったのです。そして、夕方に舎監と寮長が来ると、起立して第16号室総員何名、事故者ゼロ、と報告する。また、「一部1年甲組柳井、誰々に用事があって参りました」「一部1年柳井、誰々に用事が終わって帰ります」なんていうのは軍隊生活の経験のある方は(軍隊と)そっくりだということが分かると思います。
(註)の素絢は『論語』の「八?」篇の「素以為絢兮、何謂也」から採ったもの。素は白の意で人の生まれながらに持っているもの、絢は彩色の意で儒学的な道徳を身につけること。素絢寮で自己陶冶せよという意味か。(スタッフ)
次の頁に寮生活の一日というのがありますが、朝、700人の男ばかりの所帯ですから、太鼓のなる音で起こされ、洗顔を済ますと、故郷に向かって遥拝、全員校庭に出て朝礼。天つき運動とか乾布摩擦をし、その後「聖辞」を寮長の後について一節ずつ、唱えるのです。
<教育ハ皇化無窮ノ光輝タリ 我等今日一行ヲ修メ一進ヲ得ル コレ国家ノ進運ニ参スル所以 皇国ノ隆替懸カッテ此ノ一事ニ在リ 我等深ク 聖訓ニ恪遵シ 清明ニシテ周慎 闊達ニシテ堅忍 誓ッテ 皇国教育ノ幹トナラン>
 これを毎日言わされるのです。要するに義務教育教員養成機関としての群馬県師範学校は「本校は畏くも昭和9年11月15日、天覧授業」があり、その部屋は玉座といって保存されていましたから、軍国主義、皇国主義の世の中だったんですね。4頁に昭和16年当時の群馬師範の全図があります。校庭には400mのトラックがありました。いま、商工会議所になっているところです。付属小は現県立図書館です。寄宿舎から教場まで下履きを履かなくても上履きのまま行けたのです。教練や体操のときは靴履きでしたが。師範はそういう組織でした。以上です。
これを毎日言わされるのです。要するに義務教育教員養成機関としての群馬県師範学校は「本校は畏くも昭和9年11月15日、天覧授業」があり、その部屋は玉座といって保存されていましたから、軍国主義、皇国主義の世の中だったんですね。4頁に昭和16年当時の群馬師範の全図があります。校庭には400mのトラックがありました。いま、商工会議所になっているところです。付属小は現県立図書館です。寄宿舎から教場まで下履きを履かなくても上履きのまま行けたのです。教練や体操のときは靴履きでしたが。師範はそういう組織でした。以上です。
平野:(笑いながら)すごいですね。寮の室内の配置は迂闊にも見過ごしていましたが、本当にタテ社会そのものなのですね、上意下達というか。御著書の方にも師範学校を創った森有礼のことに触れておられますが、彼のモチーフでは国民からなる軍隊をどう作るかということと、学校つくりということが直接連動していたわけですが、それを師範学校は見事に表していたのですね。つくった当初は、軍隊と学校の違和感とかズレという感覚はまるでなかったんだろうと思います。正に近代国民をつくることと近代軍隊の兵士をつくることはストレートに結びついていた、そしてその未来の兵士を育てることが教師の第1の役割ということになっていたというリアルな師範学校の様子が良く伝わってくる話でした。
で、そのことに関わって、興味深いエピソードとして、上級生のいじめみたいなものがあったようなのですが、その辺のお話を伺いたいのですが…。
3.敷布の下に人骨?!
柳井:私の母は婿取りで実家でしたから、他所に泊まりにいったことがなかったんですね。だから、師範の寮が初めての外泊経験だったのです。入学して二日目の夜、寝床につくとまもなく、1年生は全員知道館に集まれ、と放送があったんですね。畳一枚に一人の割合で正座、広い柔道場の周りには4年生が線香を持って立っていて、線香の匂いがなんともいえない雰囲気を醸すんですね。(笑い)正面には理科室から持ってきた標本の髑髏の眼に青色の電球が光っている。師範学校は(昔の)清王寺町にありましたが、「清王寺」というお寺があったのだそうで、掃除のときなど穴を掘ると、時々人骨が出てきたりするんです。師範学校の七不思議というのがあり、当時の骨の出る部屋とか、開かずの便所のことなどをさも恐ろしげに4年生が語るのです。私は田舎者ですから、ただ恐ろしくて耳を塞いで聞かないようにしました。その後、校庭を回って、順序を教えてね、一人ずつ、回らせるのです。途中4年生がマント被って脅かしたり、線香持ったり、音楽室ではピアノを低音でさも恐ろしげに鳴らす。ところが私は出席簿が「ヤ」だから遅い、夜中になってしまい、もういいやということで、順番が回ってこなかった。ホッとして寝床に就いて寝ようとしたら敷布の下に骨のようなものがある、びっくりして飛び起き、恐る恐る見たら木刀や竹刀が入っていた。これが「試胆会」というものでした。
それから、「泣会」(漢字をどう当てるかは定かではない)というのでしょうか、上級生が制裁を加えるんです。男きりの世界ですからね。4年生が知道館に集まれ!と号令をかけ、遅れまいと走っていくと、一人一人立たされて、「何号室の誰々来ました」と言うと「貴様、生意気だ」「お辞儀しなかった」「サボったな」とぴんぴん殴るんです。ピンタの音が暗闇の中で響く。震えて待っていました。ある種の「忠告会」のようなものでした。上級生を知っていると殴られなかったらしいのです。私はたまたま「泣会」で殴られたことはなかったのですが、ある時、予科3年の上級生に寝室に呼び出され1回だけ「態度が悪い」と叩かれたことがありました。
5頁をご覧下さい。「学校の生活」のところに時間表がありますね。教練とか音楽の時間があります。特に音楽には毎週ピアノ検定というのがありました。ピアノは原小学校では一台だけ、いつも鍵がかかっていた。(大笑い)最初から両手でバイエルを弾かせる、音楽練習室にはオルガンが何台もあるので、日曜日も外出しないで練習したんです。私に廻ってくる順番が遅いから、真夏の暑い日にはみんなの汗で鍵盤がぬるぬる滑って(笑い)ドを押したのがレに行っちゃたりして(笑い)、それでもやっとの思いで何十番かにいったんです。そしたら学徒動員。やれやれ、これで嫌いなピアノを弾かなくて済む。だから、今もって弾くことが出来ません。
また、写真にありますように配属将校というのがおりまして、少佐でした。後ろの軍服の二人は中尉と少尉で教練を担当していました。以上です。
平野:今伺った中で、ふと、思い浮かんだんですけれど、入学早々にあった「試胆会」は、もしかしたら師範学校特有のものというよりむしろ旧制中学的な文化を模倣したような気がします。旧制中学のモデルというのには例えば英国のパブリックスクールがあり、ここでは新入生のイニシエーション=入会儀礼というのをやるわけです。さっきの話にあったような、結構酷いことを経験させ、共同意識をつくるというようなことをやっているのです。もっとも、「泣会」のような暗闇にピンタの音が響くという風景は軍隊の入営生活を彷彿とさせることですがね。そのことと関わって、是非お聞きしたかったのは一部生と二部生との間の確執の件なのです。どういう事件だったのかお話いただけますか。
4.確 執
柳井:寮では前にも言いましたように、一部と二部の生徒が同居していたのです。
一部生というのは(私がそうなのですが)、高等小学校卒業者で就業年限5ヵ年、二部生は中等学校卒で就業年限2ヵ年なのです。ところが、男の社会で異質なものが―一部生は小さいときから師範で厳しく訓練されおり、世の中のことは余り知らないで上級・下級生などの秩序の中で生真面目に育てられているけれど、二部生は中学から来るので世の中のことを少しは知っていて、比較的自由だった―同居していたので、なにかと軋轢みたいなものがあったのかもしれません。私が入学した昭和17年4月29日(天長節)の夜中、一部4年生(年齢的には一級下)と二部2年生の間で暴行事件(集団リンチ)が起こってしまったんです。私はちょうどその夜は「不寝番」(提灯つけて寮の内外を見回りする)でした。ところが、私には何が起こったか分からないし、上級生も説明してくれませんでした。翌朝、1年生は雑巾持って知道館(柔道室)に集まれという。そこへ行くと上級生が畳の上の血を拭けという。私は柔道の練習で流れた血だと思いましたが、それにしては大量すぎる。その時、都丸十九一先生が専攻科にいたんです。後で聞いたのですが、関茂寮長が専攻科の寮に飛んできて、事件を知らせ相談に来たというのです。一部5年に船津安男(予備学生で出陣、戦死)さんという方がいてこの人の日記を読むと、「一部4年生、二部2年生を殴打負傷せしめて一同集団脱走す」とありました。私の手帳には「4年生は全員、家に行く」とあります。
事件の概略は次のようでした。発端は二部2年生の一人が一部4年生の誰かを殴ったらしいのです。その時5年生は1学期間教育実習に出ていたので、4年生に寮の実権を任せていたのですね。そこで、4年生が二部2年生を夜中、知道館に呼び出し、退学覚悟で目潰し、木刀などでリンチを加え、全員家へ帰ってしまったんです。注意深く、交番の前は通らなかったようです。1ヵ月後学校へ戻ってきたのですが、当時は戦争中、ましてや先生になる学校で集団リンチ事件を起こしたことが明るみに出たら大変な騒ぎになったかもしれません。教官が犠牲者を一人も出さず、新聞に出ないよう不眠不休の努力をして、事を収めたらしいのです。後になって寮にいた古川丈夫先生(舎監長)や担任で教練の教官・久保田先生が辞表を出して事を収めたと聞きました。
実は師範学校ではこの一部・二部生の対立というのは何度もあったようです。一部4年生というのは軍隊で言えば古参兵で二部2年生は上級生とはいえ、寄宿舎では新兵なのです。(それに加え、先に言いましように)異質なものが同居しているのですからいろいろ対立が起こっていたのです。
大正13年に一部4年生と二部生徒の暴行事件あり、処置に不満の二部生が同盟休校したため74名全員が無期停学の処分を受けたと『上毛新聞』に報道されています。で、今回の事件も同年11月の県会にも取り上げられ、議事録にも記載されています。一部生と二部生の対立に関しては以上です。
平野:そこの対立の原因のところをもう少し詳しくお話願えませんか。端的に言って、一部生と二部生は日常的に反目の感情を抱いていたのでしょうか。
柳井:一部生と二部生は同学年でも学級が違うのです。寮では一緒ですが。それに、二部生は外の空気を知っていたし、わりあい自由に発言したり、行動したりしていましたね。だから、(人間的としての)幅が広かったですね。片方の一部生は高等小学校を卒業以来(師範で)真面目に育てられ、自由な生活に慣れていないから、自由な態度や言葉づかいなどを気に食わないというか、感情的な反発があったんですね。それに、一部生には我々が師範の本流という気持ちがあったのかもしれないですね。
平野:先生ご自身もそういう感情は持っていらっしゃいましたですか。
柳井:そうですね、私は学制改革もあって6ヵ年間師範にいましたから、中学から来た人に比べれば師範に対する愛着が違うと思うんですね。私たちにとっては師範が母校で、全てですから。
平野:要するに二部生はそういうことも知りもしないくせに生意気な口を利くというような反発が…。
柳井:(口ごもりながら)そうですね。
平野:森有礼以来の日本の教育政策には学問と教育の峻別と云う考え方があります。義務教育は学問ではない教育を行う場である、学問については上級学校に行った者だけがすればよい、というような別け方です。旧制中学はいわば学問をする準備教育の段階と位置づけられていました。これは又聞きなのですが、(旧制)中学に入るとそれまでの小学校とはがらりと先生の態度が変わって、「ここだけの話だよ、学校以外で話してはいけないよ」という但し書きを付けながら、歴史や皇室などについて「実は…」という形でそれまで教わったこととは違ったことを得々と、しかも、エリート意識をくすぐるような形で話してくれた、というのです。つまり、(中学に進むと)教育とは本当のことを教える場ではないのだ、本当のことは学問をする人間だけが知っていれば良いと言われ、ああそういうものなのかと思う者もいれば反発したり不信感を抱くもの、その気になって天狗になってしまうようなエリートもいる、というようなことを伺ったことがあります。
そこで、中学校をへて師範二部に来るという人たちはどういう事情でそういう進路の選び方をするのか、ご存知でしたら…。
柳井:親や親戚の人が教員という人が多かったみたいですね。
平野:そういう人たちは、教師にしたいが師範学校だけではなく中学校教育も受けさせて教師にしようというような意識が働いているのですかね。昭和の初め頃になるとそういう人々が現れる。しかし、一方で、そういうゆとりのない層は高等科から一部に入り、いわば純粋培養の師範教育を受ける、ということになる。
柳井:それから、中学校卒で教員になると代用教員で正規の免許状を貰えない、師範学校を出なければ正規の訓導にはなれないということもあると思う。私の同級生には代用教員をして(師範に)入ってきた人が何人かいましたが、年齢が下の上級生に叩かれるのが嫌で辞めていった人も少なくありませんでした。
5.鉄の錬成へ一直線
平野:そういう点も軍隊と一緒ですね。資料の6頁に「戦場運動」の写真がありましたが、師範学校独特の「錬成の体育」とはどういうものか、お話下さい。
 柳井:「錬成の体育」とありますが、「錬成」というのは体操ばかりではないのです。資料の1頁に「右者本学年間克ク錬成ニ努メ成績優秀ナリ」という賞状がありますが、これは高等科の優等賞なのです。教練も「錬兵」といって、教練の教官が「錬成の錬は糸偏でなく金偏だぞ」と始終言っていました。体操も体錬科でした。体力章検定制度というのが出来まして、初級から上級まであり、種目には重量運搬・俵運び・手榴弾投げ・懸垂などがありました。柔道・剣道も実戦さながらでね。戦争が激しくなる昭和17年秋に、師範の校庭で県下中等学校の柔道大会が行われました。柔道は皆さん畳の上で行うものと思っているかもしれませんが、戦争の真っ盛りはそうではないのです。戦争は実戦だ、というのでシャベルで土を掘って柔らかくして校庭でやったのです。剣道も戦場は平らなところばかりではないというので、わざと起伏のある築山を選んで、しかも、「面」、「こて」ではなく、相手が「まいった」と云うと「勝負あり」というのです。(笑い)女子師範でも銃を担いでやったのです。10月29日より「第13回明治神宮国民錬成秋季大会」(この年、国民体育大会が改称された)が開催されましたが、剣道は袴ではなくズボン姿、相撲も四股は踏まず戦場の気持ちで、当時の『朝日新聞』を見ますと「競技場は戦場だ、鉄の錬成へ一直線」、「この錬成場は、直ちに戦場に通ずる」(小泉会長)とあるように戦時色の強い大会でした。特に体操は戦争に勝つために錬成に努めよということでした。以上です。
柳井:「錬成の体育」とありますが、「錬成」というのは体操ばかりではないのです。資料の1頁に「右者本学年間克ク錬成ニ努メ成績優秀ナリ」という賞状がありますが、これは高等科の優等賞なのです。教練も「錬兵」といって、教練の教官が「錬成の錬は糸偏でなく金偏だぞ」と始終言っていました。体操も体錬科でした。体力章検定制度というのが出来まして、初級から上級まであり、種目には重量運搬・俵運び・手榴弾投げ・懸垂などがありました。柔道・剣道も実戦さながらでね。戦争が激しくなる昭和17年秋に、師範の校庭で県下中等学校の柔道大会が行われました。柔道は皆さん畳の上で行うものと思っているかもしれませんが、戦争の真っ盛りはそうではないのです。戦争は実戦だ、というのでシャベルで土を掘って柔らかくして校庭でやったのです。剣道も戦場は平らなところばかりではないというので、わざと起伏のある築山を選んで、しかも、「面」、「こて」ではなく、相手が「まいった」と云うと「勝負あり」というのです。(笑い)女子師範でも銃を担いでやったのです。10月29日より「第13回明治神宮国民錬成秋季大会」(この年、国民体育大会が改称された)が開催されましたが、剣道は袴ではなくズボン姿、相撲も四股は踏まず戦場の気持ちで、当時の『朝日新聞』を見ますと「競技場は戦場だ、鉄の錬成へ一直線」、「この錬成場は、直ちに戦場に通ずる」(小泉会長)とあるように戦時色の強い大会でした。特に体操は戦争に勝つために錬成に努めよということでした。以上です。
6.根本方針は不変不動
平野:戦争真っ最中の師範時代でしたからよりそういう色彩が強かったのだと思います。しかし、昭和20年、先生の在学中に敗戦を迎えるのですが、それを境に師範教育がどう変わったのかということをお聞きしたいと思います。
柳井:私はその当時、学徒動員で小泉の飛行機工場に行って「零戦」とか「銀河」という海軍機の組み立てをしていました。後で行き会って知ったのですが、無着成恭さんも小泉にいたそうです。で、空襲にあって、前橋に引き上げてきて、いまの前橋文学館の前に交水社という製糸工場があり、そこが飛行機の部品を作っていたので、女子従業員にドリルの使い方とかリベットの打ち方を教えていました。前橋にも空襲があり、焼け野原になってしまったわけですね。
で、師範学校の授業がいつ再開したのかと思って、たまたま日記を見ましたら、9月17日の所に次のように書いてありました。
<朝からいやな雨だ。今日から一年三ヶ月ぶりの授業が始まるのだ。五時起床、神社参拝に行く。十時講堂集合、本二・予一は十月末まで休み、我々はその間勉強なり。二部授業である。一時間、学校長(橋本重次郎)より、「デモクラシーの意義」を聞く。次は担任の高井浩教官の訓示、自分は本科一年一組である。
吾々は、大東亜戦争必勝の為に、昨年六月動員学徒として、勝たんがために敢闘致したが、結果は敗北となってしまった。吾々一億の胸中如何ばかり、今日から新国家再興のため、皇国護持の学問をやろう。悠遠の真理探究のため。>とありました。
この「皇国護持」ですが、翌日に受けた「教育学」の私のノートには次のように記されていました。この先生は後に日教組の講師団を務めたことのある方です。(笑い)
<日本教育の基本方針、どういふ事態に即応しても、根本方針は不変不動である。聖旨奉公、皇運扶翼、国体護持、右記の目的無きは日本教育でない。日本教育である限りは、どういふ事態になっても右記の目的は変わらない。「教育勅語」に、「教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」とあるが、「此」は国体である。教育の淵源―国体の精華。
天皇統一の国体である。憲法第一条に「大日本帝国ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とある。之が国体の精華なり。ポツダム宣言受諾も之を意味する。
教育の最高主体=天皇。日本の教育者は之をもって教育に当たってゐる。天皇がご自分の御考へで国民教育を行わせている。大命奉公。吾々は大命奉公によって子供に当たる。個々の教育。
大命の具体化。教育者は大命を具体的に実現してゐる。それは、戦争中、終結といえども不動である。戦争終結の勅語の御聖旨を奉公する。>
こういうのです。(笑い)
平野:これは先生が授業中、筆記なさったのですか。(すごいの声)
柳井:そうです。今日持ってくればよかったですね。そっくりノートしました。
平野:すごいですね。真面目な学生、恐るべし、ですね。すいません、途中で口を挟みまして…。
柳井:敗戦後いろいろな人が復員してきて、二部に続々入ってきましたね。8月15日ですっかり変わったといわれていますが、『師範学校』の中に載せておきましたが、私の先輩の船津安男さんは特攻隊で戦死したのですが、「海軍少佐船津安男殿ノ名誉ノ戦死ヲ悼ミ謹ミテ弔意ヲ表ス 昭和二十年十月二七日 海軍大臣米内光政」10月になっても海軍大臣がいたんですね。日本は8月15日の敗戦で、次ぐ日から民主主義国家になったのではないのですね。戦争中とちっとも変わらなかったというのは教育学の先生の講義からも分かりますね。 以上です。
平野:この当時の学校教育は勤労動員で生徒は教室にいなかったわけで、8月15日を境にして教育がガラッと変わったというよりも生徒にとっては勤労動員を挟んでその前と戦後再開された教育という間にタイムラグがあるわけですね。それにしても再開後の第1声は注目に値するわけですが、その混乱振りというか、戦前との整合性を取ることに汲々としていた教官の様子が良く分かりました。そういう中で、21,22年と少しずつ変わっていくことになるわけですね。それではこの辺で休憩を入れて後半に移りましょう。
*******************
<休 憩>
****************** 7.
「聖」とは天皇のことか
司会:それでは後半に移ります。まず、質疑から入りますが、質問やご意見をどうぞ。
 意見:先ほどなぜ師範学校へ子どもを進学させたのかが話題になっていましたが、叔父が師範学校で、勢多農林を卒業後二部に行っています。そういうのは珍しくて何人もいなかったと聞いています。私の父の兄弟は男ばかり3人で、それで、なにか家訓があったらしく「長男は米を作れ、次男は人を育てろ、三男は国を守れ」というのだそうです。(驚きの笑い)で、長男が私の父で農家を継ぎ、次男が師範学校を出て教員、三男が幼年学校から陸軍士官学校を出て、昭和18年にビルまで戦死しています。そういうことが表向きはあると思うんです。もう一つは、師範学校も士官学校もみんな無料なんですね。あんまり大きくない農家では、家の場合は祖母が婿取りで2町歩位貰ったらしいのですが、大学までの学資は無理だったのだと思います。そんなことがありました。
意見:先ほどなぜ師範学校へ子どもを進学させたのかが話題になっていましたが、叔父が師範学校で、勢多農林を卒業後二部に行っています。そういうのは珍しくて何人もいなかったと聞いています。私の父の兄弟は男ばかり3人で、それで、なにか家訓があったらしく「長男は米を作れ、次男は人を育てろ、三男は国を守れ」というのだそうです。(驚きの笑い)で、長男が私の父で農家を継ぎ、次男が師範学校を出て教員、三男が幼年学校から陸軍士官学校を出て、昭和18年にビルまで戦死しています。そういうことが表向きはあると思うんです。もう一つは、師範学校も士官学校もみんな無料なんですね。あんまり大きくない農家では、家の場合は祖母が婿取りで2町歩位貰ったらしいのですが、大学までの学資は無理だったのだと思います。そんなことがありました。
司会:貴重なご意見有難うございました。
質問:資料の8頁に敗戦後の10月30日に橋本重次郎校長から「デモクラシーについて」学んだと書いてあり、「自由は光なり」(学校長)(註)が掲示板に掲げられたとあります。で、ここに当時の師範学校での戦前の天皇制教育と戦後の民主主義教育の関係を考えるヒントがあるように思うのです。デモクラシーを説く校長先生が、一方で「理想の極地、即ち至真、至美、至善は無礙無障の自由の境地にして各々聖に通ずべし」と言っているのです。この「聖」を天皇とすると、戦前は「教育の淵源―国体の精華」、戦後の「デモクラシー」は真・善・美が「聖=天皇」に通ず、ということで両者は余り矛盾なく整合されるんですね。つまり、戦前と戦後は連続しうる、していると思えますよね。この「聖」を天皇と読み替えていいのでしょうか。
(註) 自由は光なり
真理が自由の森厳なる脚光を浴びて邁進するとき、科学を生じ/美が自由の皎雅なる光を受けて躍動する所に芸術あり/善が自由の豊潤なる光の下に具現する時、道徳となるべし/聖が崇高なる自由の光に燃ゆる時、真の宗教出ずべきなり/理想の極地、即ち至真、至美、至善は、無礙無障の自由の境地にして各々聖に通ずべし
平野:真・善・美はカントから来ているのでしょうね。橋本校長はドイツ哲学だそうですから。「聖」…。
 意見:クリスチャンなら「聖」は神でしょうが、(日本では)当時は神道で、神といえば現人神=天皇でしょう。とりわけ、敗戦間際から敗戦後も国体護持こそが何よりも大切だったし、文部省でも「大詔の聖旨を体し奉り、国体護持の一念に徹し、<中略>深遠なる聖慮に応え奉らしめんことを期すべし」(文部省訓令昭20年8月15日)を学校長に通達したとあります。ですから、この「聖」は天皇のことではないかと…。
意見:クリスチャンなら「聖」は神でしょうが、(日本では)当時は神道で、神といえば現人神=天皇でしょう。とりわけ、敗戦間際から敗戦後も国体護持こそが何よりも大切だったし、文部省でも「大詔の聖旨を体し奉り、国体護持の一念に徹し、<中略>深遠なる聖慮に応え奉らしめんことを期すべし」(文部省訓令昭20年8月15日)を学校長に通達したとあります。ですから、この「聖」は天皇のことではないかと…。
<開場からドイツ哲学の絡みではないかとの声>
平野:勿論、基本的にはドイツ哲学です。しかし、橋本校長がこの「聖」に何を込めたかはかなり微妙ですよね。実際、「八紘一宇」など近代西欧哲学を超えたと称した京都学派の人たちはドイツ哲学の流れをくんでいるのです。橋本先生には当然、そのようなことは念頭にあっただろうし、一方で文部省からの通達もありますから、校長として何らかの指針を出さなくてはいけない。ですから、さっきのような「聖」解釈が橋本校長の中になかったとは言い切れませんね。
柳井:とくに天皇と思ったようには記憶していないのですが。
質問:ここは私の一番知りたいところなので、少し突っ込んだ聞き方をしますが、柳井先生ご自身を含め、当時の学生たちは、
皇国護持の学問とデモクラシーの両方の話を先生たちから聞いたわけで、それに対して、両者に矛盾はない、そう云うものだと(肯定的に)受け止めたのか、それとも疑問に思ったのかをお聞きしたいのですが…。
柳井:急速に世の中が変わって、先生たちも私たち学生も混乱していましたからね。急に自由主義・民主主義を説く先生もいれば文部省の通達を守る先生方もいる。左と右の両方を聞き、ますます混乱して日記も書けなくなった自分がいました。そういうときに、私は国沢先生の家に行って『空想から科学へ』(エンゲルス著)の輪読会をするようになっていました。
8.教員もいろいろ
 意見:先ほど、どなたかから意見が出て、旧制中学から二部に入るものと高等小学校から一部に入るものとがいるのはどういうことだったんだろうとの意見がありましたが、私は昭和6年に二部に入ったんですけど女の人と男の人は少し違うのではないかと思うのです。私の友達の旦那さんは大学へ行くために旧制前中に入ったんだけど、就職難で、師範なら全員教員になれるので、方向転換して群馬師範の二部に入ったんだと聞きましたよ。そうしたら他の人たちにも同じようなことがあったみたい。私の旦那さんは一部だったんだけど、その当時の二部にはものすごく優秀な人がいたと言ってました。特に長男で、就職できないと困るという人の中に、大学へ進学しないで師範二部を選んだ人がいたみたい。だから、一部、二部の人たちは、時代によって入学する動機が違ったように思えます。女子はそんなことは全然考えなかったですけどね。それと、私の旦那さんは長野の望月(北信・北佐久郡や小諸)から群馬県師範学校に来たのですが、長野の師範は松本(女子師範は長野にあった)にあり、そこへ行くより群馬のほうが近かったのです。だから、距離的な問題もあったかもしれないですね。
意見:先ほど、どなたかから意見が出て、旧制中学から二部に入るものと高等小学校から一部に入るものとがいるのはどういうことだったんだろうとの意見がありましたが、私は昭和6年に二部に入ったんですけど女の人と男の人は少し違うのではないかと思うのです。私の友達の旦那さんは大学へ行くために旧制前中に入ったんだけど、就職難で、師範なら全員教員になれるので、方向転換して群馬師範の二部に入ったんだと聞きましたよ。そうしたら他の人たちにも同じようなことがあったみたい。私の旦那さんは一部だったんだけど、その当時の二部にはものすごく優秀な人がいたと言ってました。特に長男で、就職できないと困るという人の中に、大学へ進学しないで師範二部を選んだ人がいたみたい。だから、一部、二部の人たちは、時代によって入学する動機が違ったように思えます。女子はそんなことは全然考えなかったですけどね。それと、私の旦那さんは長野の望月(北信・北佐久郡や小諸)から群馬県師範学校に来たのですが、長野の師範は松本(女子師範は長野にあった)にあり、そこへ行くより群馬のほうが近かったのです。だから、距離的な問題もあったかもしれないですね。
 意見:私は東京育ちで、昭和20年旧制中学卒ですが、繰上げ卒業で軍隊に入り、特別幹部候補生(特攻隊員)になりました。戦後、父が富士見村で農業をすると云うので、こちらで一緒に開拓をしていました。松の木を倒し、根っこを掘り起こす作業の毎日でした。ところが小学校の教員になってくれというのです。「先生を待っている子どもたちのために」どうしてもと言われ、1年の約束で昭和24年、20歳で時沢小学校の代用教員になりました。
意見:私は東京育ちで、昭和20年旧制中学卒ですが、繰上げ卒業で軍隊に入り、特別幹部候補生(特攻隊員)になりました。戦後、父が富士見村で農業をすると云うので、こちらで一緒に開拓をしていました。松の木を倒し、根っこを掘り起こす作業の毎日でした。ところが小学校の教員になってくれというのです。「先生を待っている子どもたちのために」どうしてもと言われ、1年の約束で昭和24年、20歳で時沢小学校の代用教員になりました。
当時は教員が足りずに高等小学校の卒業生を臨時教員養成所で短期間教育し、教員にしていました。戦後の6・3制で新制中学が出来ると師範出の先生はそちらに移る人が多く、小学校では教員が足りなくなったんですね。それに、当時はひどいインフレ、教員の給料では生活が大変で、師範出の教員でも民間会社に転職する人もいました。だからなおさら深刻な教員不足だったのです。旧制中学や高等女学校、工業、商業学校などの卒業生が随分代用教員に駆り出されましたよ。勿論無試験で、面接だけでした。
それから、教員を続けたい人には資格を取るための様々な方法がありました。初めは助教諭ですよね。で、通信教育を受けて、教員免許をとり、正教員となる。このグループにもいくつかあって、日大の通信教育を出た人たちは「日大グループ」、旧制前中や高中から代用教員になって、通信教育などで資格を取った人たちはそれぞれグループをつくっていましたね。私はいろいろな大学で単位を集め、正規の教員になりました。県教委でも、盛んに資格を取ることを薦めていましたね。夏期講習会に出ると何単位か貰えたのです。私もその講習を受けました。学校にはいくつかのグループがありましたね。師範出にも一部グループ・二部グループみたいなのがあり、それに、さっきのようなグループが加わっていたようです。校長会あたりでもあったんじゃないかな。教員の異動なんかにも影響したみたいでした。
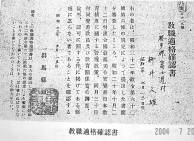 教員免許状は臨時免許状から仮免許状そして小(中)学校2級普通免許状、1級普通免許状までありました。管理職になるためには小・中二種類の免許状が必要でした。私は小学校1級と養護学校教員の免許状をとりました。1級を持ちながらまだ通信教育を受けていましたよ。在職年数で必要単位が違っていたように思います。
教員免許状は臨時免許状から仮免許状そして小(中)学校2級普通免許状、1級普通免許状までありました。管理職になるためには小・中二種類の免許状が必要でした。私は小学校1級と養護学校教員の免許状をとりました。1級を持ちながらまだ通信教育を受けていましたよ。在職年数で必要単位が違っていたように思います。
校長が管理職試験を受けろというのですが、体調を崩していましたし、ストレスで「このままだと命を保障しない」と医者に宣告されてしまいましてね。管理職試験を受けませんでした。やがて体調が戻り、養護学校の教頭を最後に定年を迎えました。
意見:私の兄は二人とも前中を出て師範二部に入りましたが、父親が教員をしていた影響だと思います。近所に高等小学校から一部に入った人がいたんですが、もう真面目一方。それに引き換え、長兄はたまに帰ってくると流行歌を歌ったり、レコードを聴いたりとのんびり、気ままな生活をしていましたから、父から見るとおよそ師範生らしくなかったんですね。寮でもああなのかなぁ、とあまりに二人が違うので心配だったようです。一部生と二部生の気風の違いのような感じがしていましたので発言してみました。
*******************
9.Learning by doing
平野:敗戦に伴い、GHQにより軍国主義除去の一環として教職員適格審査が行われたのですが、どういうものだったのですか。
柳井:前橋市に連合軍が進駐したのは昭和20年10月頃だと思うんです。県庁前に軍政本部が置かれました。ついで10月12日、マッカーサーから「日本教育制度ニ対スル管理政策」、30日に「教育及ビ教育関係官ノ調査、除外、認可ニ関スル件」の指令が出され、それに基づいて「教職員適格審査」が行われたわけです。これは現場の教職員ばかりでなく師範学校の学生に対しても行われました。資料の9頁、私の「日記」にこう記されています。
<昭和22年(1947)9月8日(月)快晴
午後1時半より「教員適格審査」のため講堂に集まる。高井浩先生より用紙2枚をもらい説明を聞く。自分等は、営門をくぐったでなし、心配は全然ないとのこと。しかし、この春の応援演説(母のいとこの県議選立候補)までも書かせたのには閉口した。これをパスしておけば、教員になってからする必要はないそうだ。もし、これをしなければ教育実習も出来ないとのこと。家へ帰って早速書いた。>
で、群馬県では103人が不適格者と判定されました。資料の12頁にその一覧がありますが、一番多いのはやはり職業軍人で、旧制中学13人、青年学校3、国民学校42、その他5、計63人でした。軍隊から復員して来た学生の中に不適格者の指定を受け、退学した人もいたようです。また、このとき萩原進さんも指定を受けました。高山彦九郎や新田義貞の暦を作ったのが引っかかった理由でした。以上です。
<フロアから、私は終戦時、幹部候補生でした。代用教員になるとき「教職員適格審査」があり、職業軍人とみなされてしまうと教員になれないため、そのことは記述しなかった、との発言>
平野:それで、教育実習にいかれたわけですが、その様子を…。
柳井:教育実習は本科3年、昭和22年(1947)10月2日から12月29日までの3ヶ月間、附属の新制中学校でやりました。当時の実習は1学期間だったんですね。途中、2週間ほど地方実習で北橘村立橘小学校へ行きました。教科は社会科を希望しました。この社会科は9月1日に発足したばかりで指導方法は模索状態でした。で、授業参観や「単元」による実地授業をして指導を受けたのですが、模索状態でしたからどうやってよいのか皆目分からない。そこで『文部省学習指導要領社会科編Ⅱ』の読み合わせをして授業を検討したり、10月22日には新高尾中学で「社会科研究会」が開かれたので参加させてもらいました。その時、教官の須田良作先生から「社会科は、児童の自発的活動が重視されてゐる。生徒自身の場に社会科学習がある」、文部省社会科係の大野連太郎さんは「社会科の方法は、民主主義に徹底した学習環境を作って、その中で実際に生活させる。問題解決を通して生徒の学習をしていく<なすことによって学ぶ>。児童生徒たちに、社会を与えていかなければならない」を学びました。以上です。
平野:社会科が始まるときに教育実習をなさった、まさにほんとのパイオニアだったのですね。で、先を急ぎますが、御卒業後、富士見中学校に赴任されたわけですね。まだ、校舎もなかったとか、校舎建築のエピソードなどお聞かせ下さい。
10.文化の発祥地!
だから村立富士見中学校…
柳井:私は昭和23(1948)年3月18日に群馬師範学校本科(註)を卒業しました。占領下でした。
(註)昭和24年(1949)6月新制の群馬大学(学芸学部・医学部・工学部)の発足に伴い、群馬師範学校はその中に包括され、群馬大学群馬師範学校と称した。昭和26年(1951)3月24日、最後の卒業式が行われ、3月31日で群馬師範学校の校史を閉じた。 (『師範学校』柳井久雄著より)
私が赴任した富士見中学には校舎がなく、私の母校原小学校の裏校舎の間借りでした。資料13頁にありますが、当時の勢多郡内の全ての新制中学には独立校舎がなかったんです。教室が足りないため午前と午後の二部授業という「不正常授業」でした。しかも、1村1中学校でしたから、富士見村の時沢・石井小学校区の生徒は遠距離通学となり、中には片道8から10kmの生徒もいたんです。午後の生徒の中には途中の山で遊んでそのまま家に帰ってしまう生徒もいる。そこでこれを「山学校」と呼んでいました。(笑い)それから、敗戦後の食糧事情から弁当を持って来られない生徒の問題や、学区意識からか生徒間の喧嘩が絶えませんでしたね。
独立校舎新築の話は『富士見村誌』(昭和29年)に詳しいのですが、田島の約6千坪の村有地を当てることとし、昭和22(1947)年9月15日新制中学校校舎建築を村当局が決定しました。ところが、その夜、カスリン台風による大水害で104名(含む小学生14、中学生5)も亡くなっちゃたんですね。ここに古屋さんが見えていますが、原東・小沢地区はものすごく死者が出てね、村議会では一時中止を余儀なくされました。しかし、日本の再建は教育によるとの村民からの強い要望で大水害の復旧と並んで新校舎建築を決め、村有林の木を売って、建設費を捻出し、それでも足りないため、整地作業などは村民の労力奉仕でやりました。かくて、昭和23年6月23日全生徒の移転が行われたんですね。原小から蟻の行列みたいに、机と椅子を担いだ生徒の列が出来てね、女の子の中には重くて泣き出す子もいましたよ。やっとの思いで富士見中にたどりついたんです。ある晩、宿直で泊まったら、夜中にピシピシと大きな音(大笑い)がして眼を覚まされた。なんだろうと良く見ていたら、大きな丸太が割れるんですね。生木を使ったからなんです。その年10月25日には第二校舎も完成、25教室となり、二部授業も解消されました。資料の14頁に、校庭に立てられた「建学の碑」がありますが、これには「新憲法の制定により、日本の進路が民主的で文化的な平和国家の建設と、之により世界人類の福祉に貢献せんとするにあることが世界に示された。この理想の実現こそ、次代を担う青少年の教育の力に依らねばならない。<中略>整然と設けられたこの富士見中学校こそ、我が富士見村文化の発祥地としなければならない。」と刻まれています。「文化の発祥地」と村民の気持ちが刻み込まれたのです。建築委員長の金子金八さんは富士見中学校の講堂に「文化の殿堂」の書を掲げたんです。これがいつの間にか無くなってしまった。学校というのは校長が変わり、時代が変わると、こういうもの(の大切さ)がいい加減に扱われるところがある、憤慨に堪えないんですがね。富士見村立というのは富士見村の人々がおおごとして建てたという意味なんですから、それを大事にしてもらわなければ…。でも、近頃は前橋と合併するなんて騒いでいますが。(笑い)余分な話をして恐縮です。
平野:でも、まさに、新しい日本を建設するのは教育に依らなければという気概の表れですよね。
柳井:校舎が建ったところは白川の川原だったところでね、大きな石がゴロゴロ、村中の人たちが毎日総出で整地したんです。村中で作った学校なんです。これからの日本は教育の力、文化の力、学校が大事だというので勢多郡で一番早く出来たんですね、
木造ですが。以上です。
平野:先生は教員をしながら最後の旧制私立大学を受験し、ご卒業もなさったと御著書にありますが、その辺のご苦労の話も伺いたいのですが。
柳井:これは、前中の知人に誘われて、師範学校の卒業式に出ないで3人で東京に受験しに行ったんです。敗戦後の当時ですから、みんな入れたんですよ。入学手続きもしてしまったのでしたが、親には内緒だし、長男だし、あのころは教員が足りなくて、富士見中学の根井吉弥校長が「やあ良く来てくれてありがたい」と確かめに家まで来てくれたんで、「お願いします」と言ってしまった。で、両方へ行くことになっていまいました。当時は蚕休み、田植え休み、稲刈り休みなど農繁休暇が沢山あったのでその時通ったんです。それで、レポート提出の科目を多く選んで昭和26年3月旧制大学の卒業証書だけもらったんです。ところが旧制大学を出ると恩典があって、高校の免許状がもらえたり、俸給が1号上がったりしたんですね。で、職員録を見て、友達が俺より1号上なんだがどういうんだと言ってきましたね。(笑い)ところが、勤評闘争で処分されたらまた同じになってしまった。(大笑い)旧大卒の資格をとったので国家公務員上級職の試験を受けたり、銀行員にでもなるか、などと大それたことを考えたこともあったんですが、特別の勉強をしたのではないのです。恥ずかしい話です。
平野:でも、国家公務員だの銀行員になってみようかとか当時は必ずしも教師一筋ではなかったのですね。しかし、それにしても、新しい教科、社会科の中身作りに意欲的に取組まれ、大きな仕事をされていくわけです。社会科教員一期生として新卒でありながら教育課程作りを一緒にしていくことになったのですが、その辺の事情を詳しくお願いします。
11.自分達で教えていいんだ
柳井:戦前の教育をした両角先生が良くご存知だと思うのですが、昔は「教授細目」があって、教科書通りに教えなければならなかったのです。教員はそっくり文部省の決めたコースをはみ出してはならない教育をさせられたんですね。ですから、松本師範附属の川井訓導は修身の時間に教科書を使わないで他の教材を使ったら即刻クビになるという大事件が起こりました。戦前は文部省の計画通り教えなければならなかったわけですね。ところが戦後になったら、教師が自分たちで教えるのが民主教育だというわけで、教える内容も自分達で計画を立てて教えられるということになったんですね。教師に自主性が出てきたわけですね。それで、社会科の教師だけで宿直の晩、三人で泊まって「富士見中学社会科年次計画」(昭和24年)を作ったんです。ですから、教師が自らカリキュラムを作れる初めだったんですかね、いままた、少し変わりつつありますが。あの当時は本当に教科書も自由、教えるのも自由、全て戦後になって解放され、全てが自由、これが民主教育というものかという感じでした。以上です。
12.村民の村民による
村民のための『富士見村誌』
平野:社会科学習を地域を教材化することによって作っていく中で『富士見村誌』へ発展していくことになるのですね。
柳井:社会科といっても教科書はないし無着成恭さんは私と同じ年齢ですが、あの人は綴方教育の方法で有名な『山びこ学校』の実践をしました。都丸十九一先生は民俗学の手法で社会科を教えました。で、都丸十九一先生が社会科をどうしようかという時に今井誉次郎先生を東京から呼んで来て研究会をするから来ないかと云うので夜、横野中学まで自転車で行き、その辺の店で今井先生を囲んで夜中まで話し合ったことがあります。あの当時の教員は教科書もないので思い思いに自分自身で考えて実践したわけですね。私は富士見村の地理や歴史を生徒と一緒に調べたり発表することで一緒に学びました。カスリン台風のことを大石進先生が一生懸命指導しました。米野宿の調査とか村の地理や歴史を生徒と一緒に調べて発表したのがだんだん貯まってきたんですね。それで、社会科を学習するには資料が作ってあれば便利ではないか、新しく来た先生も、村外から来た先生にも良いのじゃないかと言っていたら、校長が時の村長に話したんですね。文化村長だったもんだから、そういうものは村がしようということで『富士見村誌』は「村民の村民による村民のための」村誌(笑い)にしようと言うんでね、村民で作ったんです。ところが、作り始めたは良いが、誰も中心になる者がいない。そしたら、(あの当時だから出来たと思うんですが)校長さんが私に3年間、午前中は授業して午後役場に行って編纂事業をしないかというんです。それで私は午後役場に行って村誌を作ったんですね。
平野:それは教員生活何年目のことですか。
柳井:昭和27から29年の3年間ですから4年目ですか。ですから、『富士見村誌』は県下に先駆けて作ったので、編纂主任は白髪の老人かと思ったらこんな若い、25のがしてるのか、なんてよく驚かれたものです。当時はコピーもなければ写真機だって役場の金庫に1台しかない時代でしたから、どうしても3年間で作らなければというので、見切り発車でね、出来た原稿からどんどん印刷所にまわして、それでも、印刷するだけで1年以上かかりましたね。村の人たちが、いまここにも来て下さっていますが、村民が作ったというところに『富士見村誌』の価値があると思うんです。それは幼稚なところもありますが、生徒が調べたものも収録されているんです。
13.可能性としての社会科
 で、村誌は3年間で完成したのですが、その後、富士見小・中学の百人の先生たちと全教科に使える「『富士見村誌』活用計画」(昭和30年)というのを作ったんです。『村誌』を教材化するために、子どもの成長に合うように分析・再構成し、小・中学校教科別の抽出、検討して全教科の学習活動への位置づけをしたんです。それを持ち寄ってやっと出来上がりました。3ヶ月かかりましたよ。例えば、社会科中学二学年の教育の普及では寺子屋については『村誌』の何頁にあるとかね、算数の6年の円グラフの読み方では本村の自小作別農家比較図が何頁とか、全教科に当てはめて活用計画表を作って実践をしたのです。この実践(「『富士見村誌』の編纂の歩みとその活用」)を私は群馬大学の高井浩先生が所属していた「日本社会科教育学会」の学会誌(第9号1957年)に発表したんです。何年か後、上越大学の高柳英雄先生が『社会科教育研究』(第54,55号1986年)に「村誌編纂と社会科―『富士見村誌』に至る社会科実践」という論文で紹介してくれました。
で、村誌は3年間で完成したのですが、その後、富士見小・中学の百人の先生たちと全教科に使える「『富士見村誌』活用計画」(昭和30年)というのを作ったんです。『村誌』を教材化するために、子どもの成長に合うように分析・再構成し、小・中学校教科別の抽出、検討して全教科の学習活動への位置づけをしたんです。それを持ち寄ってやっと出来上がりました。3ヶ月かかりましたよ。例えば、社会科中学二学年の教育の普及では寺子屋については『村誌』の何頁にあるとかね、算数の6年の円グラフの読み方では本村の自小作別農家比較図が何頁とか、全教科に当てはめて活用計画表を作って実践をしたのです。この実践(「『富士見村誌』の編纂の歩みとその活用」)を私は群馬大学の高井浩先生が所属していた「日本社会科教育学会」の学会誌(第9号1957年)に発表したんです。何年か後、上越大学の高柳英雄先生が『社会科教育研究』(第54,55号1986年)に「村誌編纂と社会科―『富士見村誌』に至る社会科実践」という論文で紹介してくれました。
群大の中に「生活カリキュラム研究会」というのがあって、私は卒業してからも良く群大へ行きました。知っている先生もいましたし、史学研究室とか教育学の研究室などへ行って、いろいろ学びました。それで村誌を作ったり、教育の研究などもしたわけです。
この「生活カリキュラム研究会」は昭和28年に群大の垣下清一郎教授、清水幸正助教授が中心となって発足させたものです。
(すでに昭和24年東京分理科大(後の東京教育大)にコア・カリキュラム連盟(委員長:石山脩平)が結成されており、全国に広がっていた。この研究会もその支部の役割を果たしていた)
第1回研究会の課題は「社会科の諸問題」でした。その後、会の名称は「教育問題研究会」と改められましたが、隔月1回開かれ、「新教育と特別教育活動」「社会科の改善について」「単元の目標・内容・方法」などの研究発表があり、討議しました。私も県下の現場教師の一人として毎回参加し、学習しました。
それから、コア・カリキュラム連盟は昭和28年6月に「日本生活教育連盟」と改称されています。でその青年部が主催して8月には甘楽郡の神津牧場で第2回全国青年教師研究集会が「危機に対決する生活教育」をテーマに開かれ、全国から106名の参加者がいました。当時占領下の沖縄からもいましたよ。群馬県からは25名が参加しました。以上です。
平野:いまのお話は本当に興味深くって、まさに、社会科という教科が本来持っていた(或いは期待されていた)可能性、つまり、地域づくりと教育課程作りがここまで見事に連動し一体化した形で行われていたということは素晴らしいことですね。言い換えれば、地域を作ることが子どもを育てることに結びついており、しかもその内容自体も村民が作る『村誌』という形で、そこには子ども達の調査したものまで含まれていた。人づくりと村づくりをこういう形で結びつけることが出来る教科として社会科という教科が生れ、そこには豊かな可能性があったということを感じさせていただいた先生方の実践だと思いました。先ほど「生活教育連盟」の話が出ましたが、これはコア=カリキュラム連盟が改称したもので、先生の場合は社会科学習に『富士見村誌』を活用するという形でそれを実践されたわけです。
その実践の中の「歳入と税金」の実践記録が小学館の『中学社会科教育技術(6月号)』に掲載されたと御著書にありました。ここでは財政の学習に税金で親たちが悩んでいることを切り口に授業を展開しているわけですね。税金が高いということを話題にするときに、『少年朝日年鑑』の国の歳入の内訳グラフで戦前と戦後の比較が出来るように提示し、「第1図の左下の小さい円の『その他の収入』は当時の日本がいまよりずっと金持ちだったので、政府の病院とか材木の払い下げから上がる『その他の収入』が国の歳入の半分強54%を占めていたので税金もそう高くしないですんだ(以下略)」と先生が補足した、とあります。この時代の状況認識として、豊かな戦前と貧しい戦後という対比があったんだろうと思いますが(高度成長辺りでこの認識は逆転していくのだろうと思うのですが。「もはや戦後ではない」(『経済白書』がマスコミをにぎわすのは多分昭和30年代))社会科教育を通じて貧しい戦後からもはや戦後ではないという推移の辺りのことについて実感として何かありましたらお伺いしたいのですが。
柳井:経済のことはよく分からないのですが、現在は直接税が非常に多いので我々は税金が高いというのを実感するわけですが、戦前はグラフにあるように「その他の収入」が多いために庶民には直接税が少なかったと考えたのです。経済のことはよく分からないので教えてもらいたいと思います。
平野:「当時の日本は今よりずっと金持ちだった」という記述がとても印象深かったんです。当時の実感として、そういうイメージは強かったんでしょうか。
柳井:終戦直後の何もない貧しい生活から見れば良かったと言えると思うんですがね。
平野:今の子どもたちは、昔の日本は貧しかったというイメージしかもっていないのではないか、という気がするものですから。
戦前日本は金持ちだったというのはこの時代の子ども達には共有されていたのでしょうか。或いは豊かな日本が戦争に負けてどん底に落ち、もう一遍立ち直るというような感覚だったんでしょうか。
柳井:戦前もみんながみんな豊かではなかったのでしょうが、税の上からは庶民にはあまりかからなくて、他の収入が国にあったもので直接税が少なかったから、そういう印象を与えたのだと思います。
14.勤評は教員組合を変えた
平野:戦前は税が安かったんだ、そういう実感があったのかしら、と非常に印象深かったんですよ。で、富士見村において、新卒の教員でありながら新しい社会科教育作り、そして『富士見村誌』作りを通して教員としてキャリアを形成したことがその後の先生のご活躍の土台を作られたということがわかりました。しかしながらそういう順風満帆にお過ごしの中で、50年代後半勤評闘争の時代を迎え、一度逮捕・投獄されるという経験もなさるということになります。勤評闘争をめぐっての教員組合の体験について、御著書の中で、勤評闘争こそが
戦前から続く教育会的体質をもっていた教員組合を労働組合の実質を持ったものに変えたという記述がありますが、その辺の流れについて伺いたいと思います。
柳井:私は昭和23年4月に教員になりましたが、その当時は校長・教頭を始め全員が組合員だったのです。資料の17頁に昭和20年12月3日 教員組合結成準備委員会開催ニ関スル件という連絡文書がありますね。呼びかけ人の田口丁十郎と云う人は藤岡青年学校長で県の青年学校の会長、田村信一さんは同じく国民学校校長会の会長です。時勢柄「弁当御持参願申上度」とありますがね。戦前は群馬県教育会というのがありまして、戦争中は「大日本教育会群馬支部」となりましたが、教育会館はその時建てられたものです。敗戦後、教育会に代わる組織となったのが教員組合で、だから、教員組合というのは労働組合というより、教育会の延長という方が近いと思います。学校には毎朝打ち合わせというものがありますね。前日に組合の委員会や勢多支部の会議があると、その報告が行われていました。いまは組合が黒板を使ってはならないとか、部屋を使ってはいけないとか、あの頃は全員が組合員でしたから、後になって校長が抜け、だんだん抜けていきましたが…。私が組合員の時は、勢多郡の教育研究集会には主催団体として組合の他に、県教委、勢多郡町村教委、校長会などが名を連ね、指導主事と組合書記長・支部長などが一緒に企画したんです。県教組や日教組の教研集会に指導主事が一緒に参加していました。一体だったんですね。しかし、勤評闘争でがらりと教育会的な教員組合から労働組合の教員組合へ大きく変わっていったのだと思います。以上です。
平野:出来れば勤評闘争時の先生のご体験を…。
柳井:私はもともと弱いものの味方だという気持ちが大分ありまして。『富士見村誌』編纂が終わりましたら、勢多支部の書記長に選ばれたんですね。
平野:そこの経緯は…、教育会的教員組合で書記長に選ばれるのはどういう感じだったんですか。
柳井:あの当時、勢多支部長には教頭会でも代表的な人がなったんです。その人は支部長が終われば校長になった。書記長もみんなから選ばれてなったんです。そのときは(勢多支部では)千人もの組合員がいました。昭和32年(1957)勢多支部の専従書記長になったんです。そのときは校長の大部分、教頭は全員組合員でした。
平野:そうすると、書記長に選ばれたというのは一種の出世に近い感覚だったのですか。
 柳井:そうですね。で、昭和33年勤評反対闘争が盛んになったときに県教組の第二情宣部長になったんです。ところが勢多支部は大郡なのに本部に専従を出していなかったんです。ですから、私は本部役員のうち一人だけ専従ではなかったのです。
柳井:そうですね。で、昭和33年勤評反対闘争が盛んになったときに県教組の第二情宣部長になったんです。ところが勢多支部は大郡なのに本部に専従を出していなかったんです。ですから、私は本部役員のうち一人だけ専従ではなかったのです。
たまたま、「西の高知、東の群馬」と言われるほど激しく勤評反対闘争を闘いました。二晩続けて徹夜したこともあるし、県の教育長と団体交渉(註)していたとき、県庁職員が帰宅し、翌朝出勤する姿を見ながら、まだ立ちっぱなしで交渉していました。県教育会館の庭では断食闘争(5月15日より)なども行われたし、県庁構内で開いた反対集会の時には女性教員も機動隊員によって実力で退去させられたこともありました。
(註)「4月25日には、県教組は組合員二割(約1300名)が参集して県庁前道路上に押しかけ、気勢を上げながら再三交渉を要求した。(中略)教育委員会も、これ以上の混乱を避けるため、その申し入れに応じ、場所を教育長室に移して教組側の申し入れに応じたが、25日の県側のとった措置に対し轟々たる怒声による抗議がなされ、話し合いは26日朝9時半まで及んだ」(『群馬県教育史戦後編』昭和42年)
6月26日、高知では10割休暇闘争に入りました。私は3人で高知へ応援に行きまして、前日の25日、戦術会議に傍聴していましたら、中には「止めたらどうだ」という意見も出るんです。すると、「離島の分校の先生は前日の3時頃船に乗って出ちゃっている」(笑い)今更止められない。決行だというのです。そしたら数千人の組合員が高知城の庭を埋め尽くして、高知市内をデモ行進した。私らも群馬県教組というでかいタスキをかけてはりまや橋のところを通ったら一人のおばさんが「私は群馬県人です。懐かしくて」ととんできましてね。
10月25日、停職10人、減給19人、戒告163人、計192人が行政処分されました。私は停職2ヶ月の処分でした。資料18頁に処文書と処分説明書があります。
10月28日、渋川で県下4ブロックの集会が開かれましたが、赤ん坊を背負った女性教師が何人も参加していました。
10月29日、県教組本部の家宅捜索が行われ、私の家も受けました。来ると本棚などの写真を撮っていくんですね。私はプロレタリア文学書などは蔵にしまっちゃいましたから見つかりませんでしたが、「歴史の先生ですか」なんていっていましたね。11月20日の晩秋の早朝に逮捕されたんです。もう私たちが逮捕されるのは分かっていましたから、洗面用具などは風呂敷に入れてみんな用意しておいた。それで晩秋の寒い朝、ジープで来たんです。母は少しも慌てずに「ご苦労様です。いま支度していますからしばらくお待ち下さい。」と頭を下げて、それから一語も発せず、身動ぎもせず正座し続けていましたね。私は風呂敷を持って刑事の前に出ましたが、手錠はかけられませんでした。早朝、前橋警察所の留置場に収監されたわけです。すぐ後ろが済生会の病院で組合員が夜、頑張れと激励する声が留置場に聞こえました。前橋の留置場に入れられてからずっと周りから組合員の激励の声が聞こえてくるせいか、真夜中にジープに乗せられて、どこに連れて行くのかと思ったら、私は河上肇の『自叙伝』を読んでいましたので、これはとっさに盥回しかとぞっとしましたね、着いたのは桐生だったですね。そこで判事の拘留尋問を受けた。私はこれで一生が終わったと思いましたね。盥回しで一生出られないのではないか、と思ってね。(笑い)いつでしたか、二重重ねの極上の箱弁が差し入れられたことがありましてね。それには色とりどりのおかずがいっぱい盛られていてね、私の父母は不況下に育ったから、一度でよいから父母に食べさせてやりたいと思いましたね。私自身、恐慌下の極度に疲弊した農村に育ったものだから、それを食べられなかったことを思い出しますよ。それから、自宅には妻宛に小・中学校の組合員から激励の手紙や電報をたくさんもらいました。遠くは福岡県からのハガキもありましたね。警察に直接来たのは見せるんです。私は、11月24日に、前橋警察署から釈放されました。多数の組合員が出迎えてくれ、妻は幼い長男を連れて迎えに来てくれましたね。
<前橋の警察署前とほるごと
逮捕されゐしときを思えり>
減給・停職の処分を受けた私は、生まれ育った村を追われました。父母が丈夫でしたし、農業をやっていて心配がなかったので、『富士見村誌』を作っている3年間、正月とお盆に休んだっきりで、後は土曜、日曜、夜と一生懸命したんです。何しろ3年間で仕上げなければならなかったですからね。それでも村を追われ、(組合の力も弱まり)誰一人振り向いてくれる人はいませんでした。群馬師範の恩師高井浩先生はかつての教え子を救おうとタクシーを頼んで奥さんと村の教育委員の自宅を廻ってくれたり、群馬県教育委員会の事務局へ行って「柳井君はこういう人間だ」と弁護してくれたそうです。恩師はありがたいと思いましたね。
15.歓 迎 郷土史研究
昭和34(1959)年4月1日付けの新聞の「教員異動」欄に、自分の名前があったので初めて転勤を知りました。普通なら何日か前に内示というのがありますよね。それが全くない、報復人事の「不意転」でした。ところが「捨てる神あれば拾う神あり」の喩え通り、前日、隣の北橘村の民俗研究者今井善一郎(北橘村教育委員)さんから1通のハガキが届きました。中央上部に大きく「歓迎」とあり、両脇に「今日(註3月30日)聞いて嬉しかったこと、砂川無罪」「今日読んで楽しかったこと、すりばち学校」と書かれ、中央下に「今井善一郎」とありました。ですから、「あゝ、そこに行くのかな」とは31日知ったわけですが、正式には新聞で転勤を知ったことになります。それから10年、今井善一郎さんや都丸十九一さんがいたお陰で郷土史の勉強が出来ました。今井さんはご自分で集めた北橘の寺子屋教育の資料をそっくり貸してくださり、それを教育史学会の例会で発表させてくれたりしました。
都丸先生の家には夜遅くまでお邪魔し、勉強のこと学問のこと、いろいろなことを教わりました。だから、私は北橘村で育てられたと感謝してます。10年間いましたが、今井さんをはじめ何人かの人が柳井君を何とかしてやるべぇと考えたんでしょうか、私の年輩かそれより若い人たちが教頭になっているんですね。「柳井君、勢多郡中の校長に柳井君の採り手がないんだよ、おめぇは僻地しかないな」というんです。それで、僻地へやらされました。勢多郡の最果ての地へ転勤しました。
<さいはての地に転勤の我のことを
母に言えずに今日も暮れたり>
当時は、教頭を村で決められた時代だったんですね。これが最後なんです。北橘で出来ることなら何とかしてやるべぇと云うことで教頭にしてくました。それから後は県で決めるようになったんです。
16.学問の気風を漲らせる
いろいろ経験を積みましたが、余分なことですが、勤評闘争で教員としては奈落の底まで落ちましたが(註)、同じ処分された仲間の中には趣味に生きたり、違う世界に行った人もいますが、私は学問こそが教員の使命、これだけは誰にも負けたくないと思いましたね。僻地の冬は部屋の中まで凍ってしまうほど寒いんですね。それでも宿直の晩は布団を敷けば眠くなるから布団を敷きませんでした。凍てつくような寒さですから頭が冴えますね。(笑い)それで勉強しました。角田柳作先生を調べたのもそのときです。で、学問の気風を私は学校中に漲らせるということが大切と思いました。私は教頭になったとき、十数名いた職員全員に岩波文庫の『エミール』を買い与えて研修の時間に輪読会をしました。学問を教員がしなければ、地域からも信頼されないし、子どもからも尊敬されないし、みんなで勉強するように努めてきました。以上です。
(註)「勤務評定反対闘争」がなぜあのように燃え上がったのだろう。私なりに思うことに一つは「逝きて帰らぬ教え児よ/私の手は血まみれだ/君を縊ったその綱の端を/私も持っていた/しかも人の子の師の名において」(愛媛県教組の一教師)。このあやまちを再 び繰り返すまいと、50万の教師が日教組に結集したのではないだろうか。「教え子を再び戦場へ送るな」が50万の教職員をつないだ紐帯であったのである。二つ目に思うことは、明治以降、日本の教師が押さえつけられてきたことへの爆発ではなかったのだろうかということである。かつて、東北の一教師が、「教員のしあわせは、一校長に握られている」といったことがある。戦前は、人事も昇給も校長の裁量であった。加えて、昭和15年(1940)まで、教員の給料は、市町村負担であった。そのため昭和恐慌のときは俸給遅延、俸給不払い、寄附強制などが続出した。教員は長い間、地域からも圧迫されていたのだった。<中略>勤務評定反対の闘いは、子どものしあわせと、民主教育、職場の民主化を闘いとるための闘争だったのである。しかし、多数の犠牲者の出た闘争であった。(免職7名、停職32名、減給127名、戒告405名、逮捕者18名)。群馬の勤務評定反対闘争の裁判は昭和42年(1967)7月26日、前橋地方裁判所で、無罪の判決が言い渡された。しかし、検事側は控訴した。東京高等裁判所で係争中、昭和44年4月2日、最高裁判所は東京都教職員組合勤務評定反対闘争事件が無罪判決を受けた。そこで、顕治側の控訴取り下げとなり、群馬の教育裁判は飲む剤が確定した(5月9日)。(『新制中学校教員の記録』柳井久雄著 煥乎堂)
び繰り返すまいと、50万の教師が日教組に結集したのではないだろうか。「教え子を再び戦場へ送るな」が50万の教職員をつないだ紐帯であったのである。二つ目に思うことは、明治以降、日本の教師が押さえつけられてきたことへの爆発ではなかったのだろうかということである。かつて、東北の一教師が、「教員のしあわせは、一校長に握られている」といったことがある。戦前は、人事も昇給も校長の裁量であった。加えて、昭和15年(1940)まで、教員の給料は、市町村負担であった。そのため昭和恐慌のときは俸給遅延、俸給不払い、寄附強制などが続出した。教員は長い間、地域からも圧迫されていたのだった。<中略>勤務評定反対の闘いは、子どものしあわせと、民主教育、職場の民主化を闘いとるための闘争だったのである。しかし、多数の犠牲者の出た闘争であった。(免職7名、停職32名、減給127名、戒告405名、逮捕者18名)。群馬の勤務評定反対闘争の裁判は昭和42年(1967)7月26日、前橋地方裁判所で、無罪の判決が言い渡された。しかし、検事側は控訴した。東京高等裁判所で係争中、昭和44年4月2日、最高裁判所は東京都教職員組合勤務評定反対闘争事件が無罪判決を受けた。そこで、顕治側の控訴取り下げとなり、群馬の教育裁判は飲む剤が確定した(5月9日)。(『新制中学校教員の記録』柳井久雄著 煥乎堂)
平野:有難うございました。まだまだ学問の気風を漲らせた逮捕後のお話を伺いたいのですが、時間が来てしまいました。
司会:時間がなく申し訳ありません。この施設は時間厳守ですので。
感想:私は柳井先生が最初に赴任した富士見中学昭和23年の生徒です。(驚きの声)(今日の話は)何十年ヵぶりに先生の社会科の授業を受けたような感じでした。何しろ非常にユニークな感じの先生でした。先生から頂戴した何冊かの本を大事にして読ませていただいております。お元気そうで何よりでございます。有難うございました。
司会:今日は時間が足りなくなってしまい、不十分になってしまいましたが、後ほど先生に補足いただき、追録と言う形でニュースに収録し、皆さんにお届けいたしますので本日はご容赦いただければと思います。有難うございました。
(文責:橋本)
〔追 録〕
橋本:勤評反対闘争に関連して、いま、東京では人事考課制度といって実質的に勤評が実施されています。教員の実績を評価して給料に差をつけ、頑張らせようという制度ですが、こういうことをいま、先生はどのようにお考えですか。
柳井:教育の本質を離れた考え方だと思いますね。工場で製品をつくるんじゃなく人間を作るのが教育ですよ。教師というのは完成されたものではなく、一生かかって教育者となる努力するわけだよね。それを一時の実績などで評価するなんてとんでもないことだと思いますよ。人間というのは成長するものですよ。もっと将来を見渡して、むしろ(行政は)教育の根本、本質、原点とはどういうものかを勉強した方がいいですね。具体的な方法は教師が各々考えればよいこと、枠にはめないで、創造的にしなければ。それは教師が学べばおのずから出てくるのですよ。教えることだって、すぐに役立つものもあれば50,60歳になって花開くことだってある。だから、教員だって良い学校を出てきた先生が良い教師とは限らないし、石川啄木は日本一の教師だって言ったけど代用教員だし、代用教員のなかには正規の教員よりよほど良い影響を与えた人も沢山いるのだから、それを学歴とか成績とかで教育を評価してはいけない。そして、うまい授業をするのが必ずしも生徒に浸透しているとは限らない。話が下手でも、教え方が拙くても、標準語を使わなくても、無着成恭さんみたいに「んだ、んだ」と言ってても、子どもに浸透すれが良いんでね。さも良い言葉で、昔「修身」や道徳の授業のときはネクタイをしてちゃんとしなくちゃダメだといわれたりしたけ時代があったけれど、支度も大事かもしれないが、それ以上に中身のことを考えなくてはね。教育の場では昔から実質の伴わない形式が幅を利かしていてね。何か計画書を出せといえば分厚い計画書を作って出すけれど、書くだけなら何だって書ける。
橋本:教員は管理職の指導の下で1年間の達成目標(数値目標)を立てるんです。だから、1年間でどれだけ目標を達成できたかというのは分かるんですが、民間企業と違って、管理職がそれをどう評価し、行政に報告したかは知らされないという仕組みなのだそうです。
柳井:それでは向上の役にたたないね。生活や地域に結びついた教育をしていけば何も点数付けたりする必要はないのにね。評価などは教育には余り当てはまらないことだよね。教育はもっと崇高と云うか、製品と同じレベルで生徒を考えてはダメだと思いますよ。そんなに簡単なものじゃない。教育とは何かというのは昔から問い続けられている問題でね、これからも永遠に問い続けられる問題でしょ。それほど難しくって分からない問題を多く含んでいる。最近の動きには驚かされますね。
橋本:(問題が少しずれますが)先にお伺いした両角、関口両先生は群馬師範の出身なのですが、師範では「疑いを持たないように」育てられたとおっしゃっているのですが、先生はどうでしたか。
柳井:(じっと考えながら)私は教育者は誇りを持て!ということを一番教えられたように思いますね。(そのために)教育者は立派な人間にならなければならない。
橋本:戦前は一定の枠を作ってその範囲内のことしか教えなかったといわれていますが。
柳井:エライ世の中だったよね、戦争中は。戦後の民主教育を模索している時代にはこれから文化国家、平和な世の中をつくるんだと教師も世の中も意気に燃えていたんですが、いまはエラク変わっちゃたよね。
橋本:「新しい歴史教科書を作る会」の歴史教科書や公民科教科書では小学校や中学校の生徒には必ずしもありのまま(学問レベルの真実)を教える必要はない。それよりも良い国民になるために誇りを持てるような歴史や文化の伝統を教えた方が良いという考えらしいのです。いま、文部省が小・中学生全員に『心のノート』を配布しましたが、心理学を応用した一見素晴らしい補助教材なのです。ところが良く見ていくと、一定の枠が作ってあって、その中にいればよい子になれるよという仕組みなんですね。どういうよい子かと言うと、国家にとってのよい子づくりなんですね。『教科書が危ない』の入江曜子さんも『新しい歴史教科書』『公民科教科書』『心のノート』が合わさって子どもを枠に閉じ込めようとしていると警告していますよね。
柳井:教員も世の中も敗戦直後の5年間ぐらいの日本人の意気込み、日本をどう建て直そうかと燃えた、あの当時に戻らなければと思いますね。子どもも先生も燃えていましたよね。それが締め付けの世の中になってしまってはね…。
橋本:枠内教育は外のものを排斥する狭い人間を育てますよね。偏狭なナショナリスト(国粋主義者)とパトリオット(愛国者)は違う。
柳井:アメリカ教育使節団が来たときには「教育というのは自由な空気を作ることだ」といいましたが、行政も管理職も学校現場に自由の雰囲気を作ってあげなくてね。学問はそういう中で行われるものですよ。
橋本:そういう意味で,先生の「学校に学問の気風を漲らせる」というのは、いま、学校に一番求められているように思えますね。
柳井:学問をやれば変わっていきますよ。学問をする事によって人間は自由になり、平等になり、平和になり、幸せになってきたんだものね。学問は幸せの歴史ですよ。無知では幸せになれない。学問しなければ教師としての価値がない。学問すれば地域から信頼され、子どもにも尊敬される、子どもが勉強を好きになりますよ。自分も気持ちが良いし、だから堂々と生きられると思うんです。短い物差しで計れば、失敗するたびにダメダメと言わなければならないが、人間は神様じゃないのだから、間違うのが普通。長い物差しで子どもを見られる力をつけるのは学問を続けていることだと思うんです。子どもだって勉強していれば長い物差しで計ることを考えるでしょ。そうすれば、一回躓いたくらいでいじめたり、挫けずに済む自分を育てることが出来ると思います。
橋本:今日はお忙しい中、長年の学問と体験に裏打ちされた貴重なご意見をいただきまして有難うございました。
(7月19日、先生宅でお話を伺いました。)
 の全教科で取り組んだ「『富士見村 誌』活用計画」の作成とその実践。しかし、教職員組合を労働組合へ変えた「勤評闘争」の代償は大きかった。逮捕され裁判闘争。社会科教育実践の原点、富士見中を追われ、北橘中へ。今井・都丸両先生の指導のもと、郷土教育研究者として教師の情熱と良心を注ぎ込む日々が続く。数々の証言。無罪判決。そして得たものは…。
の全教科で取り組んだ「『富士見村 誌』活用計画」の作成とその実践。しかし、教職員組合を労働組合へ変えた「勤評闘争」の代償は大きかった。逮捕され裁判闘争。社会科教育実践の原点、富士見中を追われ、北橘中へ。今井・都丸両先生の指導のもと、郷土教育研究者として教師の情熱と良心を注ぎ込む日々が続く。数々の証言。無罪判決。そして得たものは…。